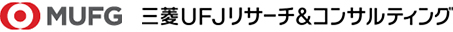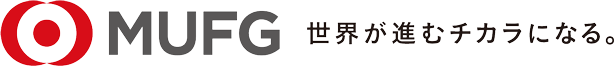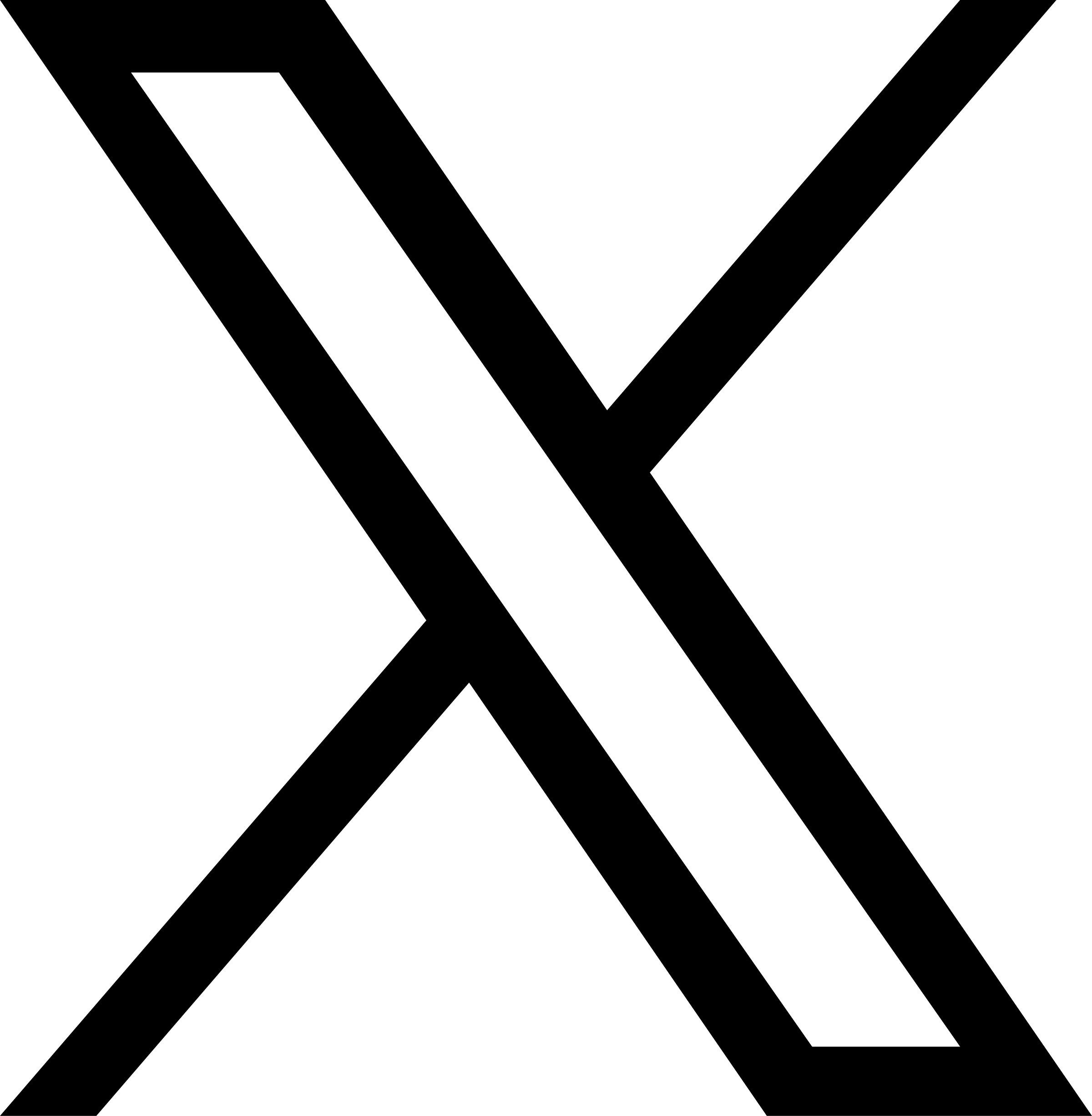教師個人の自律性、奮闘を生かすため、協働で行うCPDへ学校業務改善に向け現場で支援を行う妹尾氏と、教師教育の国際比較研究を行う百合田氏による対談
はじめに
一昨年度からシリーズで紹介してきた、国外の教師の学び直し(CPD:Continuous Professional Development)に関する政策研究レポート。調査国となったのは、アメリカ、UK(イングランド、ウェールズ、スコットランド)、オーストラリア、北欧(フィンランド、ノルウェー、デンマーク、エストニア)、韓国、シンガポール、そして国際教育学会の12地域に及ぶ。(以下「当社調査国」とする。)
当社調査国を比較すると、教職スタンダードとCPD政策が強く連関しあう国もあれば、教師の自律性を重視するためにあえて教職スタンダードを設定しないCPD政策を採用する国もあった。またCPD政策をけん引する主体について、政府、専門職能団体、地方自治体の行政機関など多様であった。
各国のCPD政策は文字通り“様々”に異なる部分もあったが、共通している部分もあった。調査対象としたいずれの国でも、教師自身が自律的に、そして省察的に学ぶことを目指しており、その傾向は日本でも同様であろう。(国際教育学会1の年大会におけるテーマを見ても、自律的な専門性開発や、ネットワークを活用した非トップダウン型での専門性開発を志向している様子がうかがえる。)
当社調査国の中で比較すると日本は国際的にも注目される授業研究(Lesson Study)の文化を持ちながら、最長の労働時間ゆえ職能開発時間が十分確保できていない特徴を持つ。コロナ禍で、教室にはタブレット端末が拡がり、そして臨時休校等を通じ学校教育の在り方を問い直した教師も少なくないだろう。学びのスタイルが少しずつ変わり始める中、教師自身の学び直しを前進させるには、どういった点が鍵になるだろうか。
今回は、学校業務改善に向け現場で支援を行う妹尾昌俊氏(教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表)と、国際的動向を踏まえた教師教育および教育政策研究を行う百合田真樹人氏(独立行政法人教職員支援機構上席フェロー)による対談を紹介し、日本におけるCPD政策前進のヒントを考えていく。

◆氏名 :妹尾 昌俊(せのお まさとし)
◆略歴 :教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表。野村総合研究所を経て、2016年から独立。文部科学省での講演のほか全国各地で教職員研修やコンサルティングを手がけている。著書に『学校をおもしろくする思考法』(学事出版)、『教師崩壊』(PHP新書)、『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)など。

◆氏名 :百合田 真樹人(ゆりた まきと)
◆略歴 :独立行政法人教職員支援機構上席フェロー。同志社大卒。政治哲学、歴史哲学、教師教育学の三領域を横断する学際的研究により、ミシガン州立大学で博士号を取得。島根大学准教授を経て、現職。2019-20年度は、経済協力開発機構(OECD)教育スキル局政策アナリストとしてパリ駐在。主に教師教育および教育政策領域について国際研究動向を踏まえた調査研究を担当。
※五十音順。以下、本文中は敬称略。
質問者の発言の前には「MURC」と記載。
教師個人の奮闘に支えられる日本の教育現場
―MURC: 本日は、コロナによる変化を嚆矢に、日本での教師のCPDの可能性を考えられればと、妹尾様、百合田様にお集まりいただきました。日本の教師の学び直しの発展可能性について、お二人からお話をお伺いしたいと思います。
まず、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)」(令和3年1月26日)について、感じられていることについて、お話いただけますでしょうか。
―妹尾: この10年、20年、教育改革の名のもとに学校で対応すべきことが次々と増えています。いくら理念がよくても、各校ではやったふり、形骸化してしまっている印象があります。ただ、「個別最適な学び」が掲げられているのはチャンスだと思っています。例えば、一部の中学校ではノートをしっかりとっている生徒の評価が高くなる傾向にありますが、生徒によって学ぶ方法は様々です。こうした学びの多様性が少しずつ認められてきたと思っており、「こうでなければならない」というのが柔軟になり始めているのではないかと捉えています。「省察的」とも言えるかと思いますが、これまで良いと思っていたことが必ずしも良いとは限らないという視点で見直していけると良いと思っています。

―百合田: 私も令和の日本型学校教育答申は1つのチャンスだと思いますが、これをどう生かすかが重要ですね。学校現場の裁量権をいかに拡充するか、そして、裁量権の拡充にあたっては、管理的な視点ではなく、責任にもとづく視点でどう具体化するか、CPDのような教師教育の文化をどう醸成していくかが鍵だと思っています。
―MURC: お二人からは「省察的」や「教師教育の文化」といったキーワードが聞かれました。では、現在の日本のCPDをどのように捉えていますか。
―妹尾: 大昔の話になりますが、1966年度に文部省が実施した教員勤務状況調査では、自主研修に費やす時間も把握されていました。給特法2ができた頃、教師には創造的で自主的な学びがかなりあったのかもしれません。今日の状況とはまったく異なりますね。わたしが2019、20年に調査したところ、読書や自主的なセミナーの参加など自主研修の取組状況は、教師間の差が大きく、学び続ける姿勢は二極化、三極化していることが分かりました。教育現場の多忙化だけが学び直しができない理由ではないと思います。それに日本では公式な研修の機会も多いとは言えないと思います。
―百合田: 学び直しが進まない原因は多忙化だけでないでしょう。教師が学び直しのために、自律的に問いを立てられるよう探究する必要性や、教師が社会変革の主体であること、学校教育が社会の格差是正の役割を担うということを確認する必要があると思います。教員養成段階でそうしたことを実感し、その具体的な意味や手段を学ぶ機会となるような、新しい教員養成を考えねばならないと感じています。 また、校長が学校の持つ社会の格差是正の役割の認識を持つことができれば、学校のあり方は変わると思います。より良い学校にするために奮闘している校長はたくさんいますが、校長個人の取り組みでとどまっており、それを後押しする行政側の支援などは乏しい印象です。
―妹尾: 戸田市など一部の自治体では、自治体レベルで取り組みを進めているところもありますが、まだまだ個々の校長の奮闘に任せてしまっている自治体が多いように思います。
―MURC: 学び直しや、学校運営などの工夫も現場の教師や校長個人の奮闘に支えられているものの、それを後押しする行政側の支援が必ずしも十分ではないということですね。
―百合田: 昨年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う休校期間の対応についても、その様子がうかがえました。休校期間中は、制度的なサポートが十分にない中で、教師の努力、教師間協働、教師の自律性に支えられ、現場は相当に頑張ったと評価できます。また、コロナ禍で見えてきたのは、効率化が教育行政にとって必ずしも良いことではないということです。
言い換えれば、諸外国で進められてきた効率化のための学校の大規模化は、公教育としての学校機能の効率化につながらないことが見えてきました。日本の、特に地方部では、大規模化が遅れており、小規模校が多い現状があります。そうした小規模校では、休校期間中も子どもとのコンタクトをとることができていました。世界的な流れだった効率化とは相反して、日本の「冗長性」がポジティブに働いた側面だと思います。ただし、こうした教師の奮闘や冗長性は前向きに捉えられていますが、大切なことは、それを可能にしたのは、個々の教師が持つ自律性の文化によるものであり、教育システムといった制度的な側面からの支えは不十分であると感じています。
現場での学び直しを支える共通基盤の不足と、教師に定着しにくいコアとなる考え方
―MURC: 変わり始める契機を活かすためにも、制度的な支えが必要ということですね。省察というキーワードもありましたが、アメリカやオーストラリア、イングランド、シンガポール等では、教職スタンダードといった専門職基準が開発され、教師がその基準に照らし、足りない部分を学び直し、職能開発を進めています。教職スタンダードとCPDが連関する潮流の中、日本でも、都道府県教育委員会ごとに教員育成指標が設定されていますよね。これらは学校現場の教師のCPDに寄与できているのでしょうか。
―百合田: そうですね、日本では、「学校教育とは何か」という認識の基盤が育まれていないと感じます。学校教育の文化、公教育を担う教師の文化を形成していく必要がありますが、今の日本の教師教育のあり方では難しいと感じます。

―妹尾: 育成指標よりもっと手前の問題として、国が示す教育振興基本計画があり、ならびにそれを踏まえて各自治体でも教育大綱や振興計画が作られているわけですが、これらが日々の授業など教育活動において、教師の中で意識されていないのではないかと感じます。学習指導要領もすべての教師が読み込んでいるかというと疑問があり、研究授業の時など限られた時のみ活用すると述べる教師もいます。コアとなる考え方が教師に十分定着していないように感じます。
―百合田:そもそも学校現場で「何が問題か」を論じるには、教師間で共通言語がないと考えられません。教師がどういった共通言語を持たねばならないか、これを教育現場から形成するのは難しく、行政や研究側から作り出さないといけないと思っています。
Column:教職スタンダードを持つ国と持たざる国
教職スタンダードについて、日本では2017年に国立教育政策研究所から公表された「諸外国における教員の資質・能力スタンダード3」において「諸外国では,教員の資質・能力スタンダードを開発し,養成,採用,研修等の指標として活用しているところも多い」としている。日本では、「高度専門職業人として教職キャリア全体を俯瞰しつつ,教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能力の明確化のため,各都道府県等は教員育成指標を整備する4」ことが決められ、各都道府県教育委員会では教職スタンダード等の指標を設定している。では国外の状況を見てみよう。本コラムでは当社調査国の中には教職スタンダードを持つ国と、あえて持たない国があった点に注目して簡単に紹介したい。
◆アメリカ合衆国: 教職スタンダードを専門職団体が設定し、CPDと関連させる国◆
アメリカでは、1980年代の「備えある国家―21世紀の教員:職業としての教育に関するタスクフォースの報告」以後、専門職団体により、研修、教員養成に関わる認証基準、および教員養成機関の質を評価する基準の策定や運用が行われて5おり、下表のとおり専門職能団体ごとに設定されるスタンダードや基準はCPDと密接に関連しているものがある。

(詳細は政策への架け橋(専門職団体、実証研究)が機能するアメリカの教員専門能力開発 諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第5弾(2021年8月17日)参照)
◆英国(United Kingdom):3地域とも教職スタンダードとCPDが関連するが策定プロセスに差異◆
英国(United Kingdom)のイングランド、ウェールズ、スコットランドの3地域のCPD政策はいずれも教職スタンダード(teaching standards)と関連したものになっている。3地域の教職基準の策定プロセスには違いがあり、イングランドの基準は外在的に課されたアカウンタビリティ(説明責任)の要素が強く、発展の過程は中央政府の強い統制下にあり、教師自身は限定的な発言権しか持たなかったこと、またこの基準が財政配分の判断基準になったことが特徴として挙げられている6。他方でスコットランドの基準の最初の発展の背後には広範な研究調査の努力と、協議過程が存在するとし、その過程の中心を担った存在として、CPDを牽引する組織でもあるGTCS(General Teaching Council for Scotland7)に言及している。
CPDの3地域の共通点として省察的である点、協働的である点、また実践とのコミュニティを重視している点が挙げられるが、CPD政策についても中央集権的なイングランドと、教師等の関係者との対話など現場の視点を重視するスコットランドとの間で違いがある。
(詳細は教員への「疑いの文化」のイングランドと、「信頼の文化」のスコットランド。英国(UK)の教員は専門職として学び続けられるのか。 諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第2弾(2020年11月6日)参照)
◆韓国:教職スタンダードをあえて設定しない国◆
韓国では教職スタンダードを作成・導入すること、また、教職スタンダードとリンクする資格を新設することについては、韓国教育部、KEDI(Korean Educational Development Institute8)共通して慎重な立場が取られている。両機関へのインタビューでは、ともに教職スタンダードを作成し教師の役割や能力が規定されてしまうと、教師の能力開発がその範疇にとどまり、硬直化する懸念が挙げられた。さらに、教職スタンダードで規定された専門性とリンクする形で教師の資格を新設すると、教師間の「序列化」や「上下関係の形成」につながり、教師同士の平等な関係性が損なわれることも指摘された。教職スタンダードのデメリットへの警戒は、教師の多様性・平等性を重んじる姿勢と表裏一体の関係にあると言える。
(詳細は教職スタンダード不在の韓国。行政からの信頼に下支えされた、教員の主体性・多様性重視のCPDの在り方とは。 諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第6弾(2021年10月1日)参照)
学び直しの体制構築を支える対話の文化と、その文化を生み出す鍵となる管理職―諸外国の取り組みから
―MURC: 学校現場で共通言語やコアとなる考え方が定着していない、との指摘がありましたが、全国の学校を回られる妹尾様から見て、学校組織という単位でコアとなる考え方が共有されているとお感じになりますか。
―妹尾: 例えば、「主体的な学び」にしても、個々の教師が授業の中で実践できている部分はあったとしても、学校組織の単位で見るとうまくいっていないこともしばしばあります。学校のビジョンがうまく共有されておらず、組織として機能できていない部分があると感じますね。
―百合田: そうなのですね。日本では、教師に限らずですが、所属する組織や社会を自分自身で変えよう、と取り組むことが苦手な印象があります。妹尾さんは、この原因をどうお考えですか?
―妹尾: 組織や社会の課題を疑問視する教師と、疑問視しない教師がいますが、疑問視しない教師は、自身が生徒の頃から学校の文化に順応してきたからではないかと思います。また、疑問に感じる教師がいたとしても、学校ではなかなか議論ができる機会がない場合もあります。実際に校内研修を見ても、授業研究が中心であり、組織として学校運営をどうするかという話はあまりされていません。
―百合田: 仕組みや制度などを変更する際には、「対話」が重要です。例えば、ノルウェーは、教育省と組合、教育委員会で常に対話し、三者間での人事交流もしています。そうした対話の文化に支えられ、教師志望者の修士号義務化も実現しました。また、ウェールズも教師研修のシステムを変え、現在移行中ですが、それに向けては、様々なステークホルダーと協働でカリキュラムを作り、カリキュラムを実行するためにどうしていくかについても、協働で検討しています。日本にはこうした対話の文化が不足していると感じます。
また、今の日本のCPDは欠損モデルに基づいています。この欠損を指摘する主体が教師自身や学校現場ではなく、その外側にある経済界などにあります。外部から過度に介入されないCPDの体制を作るには、責任にもとづく学校の裁量権の拡充と、管理職機能の変化が必要だと感じています。
Column:CPDの発展における関係機関との「対話」
日本では、2015年に出された中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~」において、地域の教育委員会と大学等との連携・協議の重要性が指摘されている9が、「教員の資質能力の向上に関する調査」10(文部科学省)の結果を見ると、「研修プログラムの企画・開発」等の連携は不十分であることがうかがえる。
では、国外にてCPDの発展におけるステークホルダーとの対話・協働はどのように行われているのか。本コラムでは、北欧と英国における対話・連携の仕組みについて簡単に紹介する。
◆北欧:地域・学校・関係機関が協働してCPDを発展させる仕組み◆
北欧(フィンランド、ノルウェー、デンマーク、エストニア)では、各国で発展経路は異なるものの、CPDにおける地方公共団体や学校の権限が大きいという特徴がある。このことが地域間格差を引き起こす可能性がある一方で、地方公共団体・学校・教員養成機関がネットワークを形成していたり(ノルウェー)、教職員組合が現場の課題に即した現職研修を提供する(デンマーク)等、各地の教員養成機関や教職員組合等の関係機関がCPDに携わり、発展させている様子も見られる。
またエストニアでは、教師の評価体系が学校内で確立されており、教師のCPDに関する計画も教師と校長の対話によって策定されている。これにより、個々の教育実践とそれに対する評価、その評価を踏まえて行われるCPDが接続し、現場や教師本人のニーズを踏まえたスキルの獲得が可能になっている。
(詳細は北欧4ヶ国に見る、地域・学校ベースの専門能力開発 諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第3弾(2021年6月24日)参照)
◆英国(United Kingdom):CPDのガイドライン策定プロセスに現場との対話を位置付ける◆
スコットランドではGTCS(General Teaching Council for Scotland)を中心に教職スタンダードの策定が行われており、その策定プロセスに教師等との協議・対話が位置付けられている。同様に2019年に発表されたCPDに関するガイドライン11についても、GTCSが教師を含む関係者との協議・対話を中心に策定しており、制度をつくる上で現場の視点を重視していることがうかがえる。既往研究でも指摘されているように「様々な人が,直接的・間接的に教員養成の質保証に向けて参画していることこそが,スコットランドの強み」12と言えるだろう。
なお、こうした特徴は各地域に共通して見られるわけではなく、イングランドでは、GTC(General Teaching Council)は現在廃止され、中央集権的にCPD政策が取り組まれているという特徴を持つ。
(詳細は教員への「疑いの文化」のイングランドと、「信頼の文化」のスコットランド。英国(UK)の教員は専門職として学び続けられるのか。 諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第2弾(2020年11月6日))
教師の学び直しを可能にするために、管理職に求められる役割とは
―MURC: 管理職の変化というお話がありましたが、管理職はどのように変化すべきでしょうか。
―百合田: 教師に研修を受けさせなければならない、という行政側のニーズがありますが、強制するのではなく、教師の自律的な学びの推進が必要です。ただ注意すべきは、教師の自律性だけに任せると、学ばない教師や関心のあることのみ学ぶ教師が出てきてしまいます。そうした教師の学びを調整するためには、学校の管理職が、その学校の教師が組織として今の課題に対応できるかを評価、判断したうえで教員組織の機能強化のために必要な研修を設計できることが必要です。管理職がそのように機能すれば、学校の裁量権を大きくすることができます。管理職には、学校が組織として課題解決できる力を持てるよう、教師の学び直しを企画してほしいと考えています。
―妹尾: 具体的に教頭、校長に求めることは何でしょうか?
―百合田: まず学校の目標を地域の状況も踏まえて立てる。その目標に基づき、学校に今どのような教師がいて、どのようなスキルが不足しているかを検討してほしいと思います。そして、個々の教師が担う組織の機能を強化するために必要なスキルを評価する際には、学校の組織目標に照らして、これまでの研修履歴を活用しながら評価し、どのような研修が必要か個々の教師と対話してほしいと考えています。
―妹尾: 今の教育現場の実態を踏まえると、お話された管理職の変化はハードルが高いと感じます。また、中央教育審議会の議論を見ていて違和感があるのは、「校長のリーダーシップの下」という言葉です。様々なところで出てくる言葉ですが、「校長のリーダーシップの下」で行うことで学校現場がどれほど変化できているのか…疑問があります。
―百合田: 確かに「リーダーシップ」を明確に定義していないですよね。管理職の変化には、行政からのアプローチが必要だと思います。①管理職が変化すれば、②学校に裁量権を与えることができ、学校に裁量権を与えれば③評価システムを変えることができます。日本は③評価システムから変えようとする傾向にありますが、評価を突然変えても、学校システム全体を変えないとうまく機能しないと考えられます。
また、私がイメージする管理職の変化を実現するにあたっては、日本では管理職の任期が短いという体制面も1つの課題だと感じています。

―妹尾: 「省察」という意味では、現在は、管理職へのフィードバックの仕組みも弱いと感じています。教師が校長の評価をできるようなシステムにできるとよいのではないかと考えています。
―百合田: ウェールズでは、独立機構をつくりスクールリーダーシップを身につけたり、評価したりする支援機関を創設しています。日本において、教師と対話しながら教師の学び直しを実現できるような管理職へ変化していくための支援は、独立行政法人教職員支援機構(以下、「NITS」とする)が担える役割もあると思っています。
協働して推進するCPDに向けて ―教育現場と他機関の共通理念の共有―
―MURC: 海外では、CPDのシステム作りに独立機構やシンクタンク等が力を発揮しているところもみられます。日本だとどういった機関がそういった役割を果たすことができるでしょうか。
―百合田: 日本で様々なステークホルダーによる共創が難しいのは、それぞれのステークホルダーが異なる方向を向いており、共通の理念がないからです。NITSは行政や教育関連の学会とのつながりも強く、実践と研究の双方の場を繋ぐことができるのではないかと考えています。ステークホルダー間で共通理念を共有しながら、協働ができると良いと思います。

―妹尾: 文部科学省や教育委員会等が示すものについて、「それが本当に必要か、なぜか」ということを学校現場の教師も交えて対話する場があれば良いと思います。国や自治体の審議の場に教師の声が届きにくいと感じています。案が固まった段階で現場に見せるのではなく、検討段階から現場の教師が議論できるような仕組みがあることが望ましいです。そうすることで、広い意味で教師のリーダーシップやエージェンシーの育成にもつながるのではないでしょうか。
―百合田: そうですね。リーダーシップが変化するためにも、管理職養成のカリキュラムモデルを作れないかと考えています。NITSで管理職登用システムと、登用にあたっての研修カリキュラムの試案を作成し、管理職の養成や登用をめぐる開かれた議論に貢献したいと考えています。
―MURC: 異なる立場のお二人から、日本のCPDの進展に必要な視点をたくさんいただきました。本日は、ありがとうございました。
インタビュアーによる振り返り
過年度の調査を通して、教職スタンダードとCPDの関係性のあり方や、ステークホルダー間の対話・協働により支えられるCPDの発展の文化、など各国のCPDの特徴を見てきた。
今回の妹尾氏と百合田氏の対談からは、日本の教育現場を支える教師個々の自律性、奮闘といった日本の強みが見えた。その一方で、日本において教師のより良い学び直しを実現していくためには、教育を取り巻く主体間の協働を促進するための共通理念が必要であることや、学校の組織力向上のため管理職機能の再定義が課題として見えてきた。今後、日本の強みである教師個々の自律性、奮闘を生かしたCPDの文化を構築していくにあたっては、教師を支える制度面、体制面の充実や、教師や学校自身が主体的に学校現場や教育のあり方の議論に参画するための仕組みづくりが重要な観点だといえよう。さらに、学校、行政、学会やNITS等の教育に関わるステークホルダーが対話や協働を通じて共通理念を持ち、日本が目指す教育の目標を共有していくことで、日本ならではのCPDの文化を作り上げることが期待される。
1 EERA(欧州教育研究協会)やAERA(アメリカ教育研究協会)を参照した。詳細は国際教育学会と教育先進国シンガポールから見る、危機の時代を生き抜く教員を支えるキーワード「CPD」とは諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見る シリーズ第1弾(2020年10月20日)を参照。
2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)
3 国立教育政策研究所よりダウンロード可能。同調査では、イングランド(以下,イギリス),ドイツ,フランス,フィンランド,アメリカ合衆国(以下,アメリカ),オーストラリア,ニュージーランド,シンガポール,韓国を調査対象としている。
4 脚注2
5 小柳和喜雄(2017)「米国のedTPAの取組についての議論に関する研究-養成と採用と研修でパフォーマンス評価を用いる可能性の検討-」, 次世代教員養成センター研究紀要, 第3巻,pp.1-10
6 高野和子(2017)「教師と教師教育のためのコンピテンスと基準」
7 1965年に制定された法律により設置されている、世界初の教職の専門職団体である。
8 韓国の政府系シンクタンクである韓国教育開発院を指す。
9 中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~(答申)」(平成27年12月21日)(2022年1月11日確認)
10 文部科学省「教員の資質能力の向上に関する調査の結果」(2022年1月11日確認)
11 「Unlocking the Potential of Professional Review and Development」
12 岩田昌太郎・濱本想子・白石智也・嘉数健悟(2019)「日本における教員養成の質保証の現状と課題:国内の研究動向からみる今後への示唆」『広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部』第68号 243-252
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。