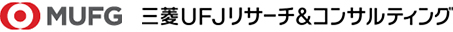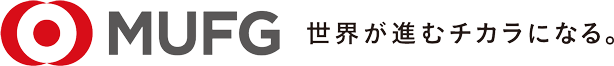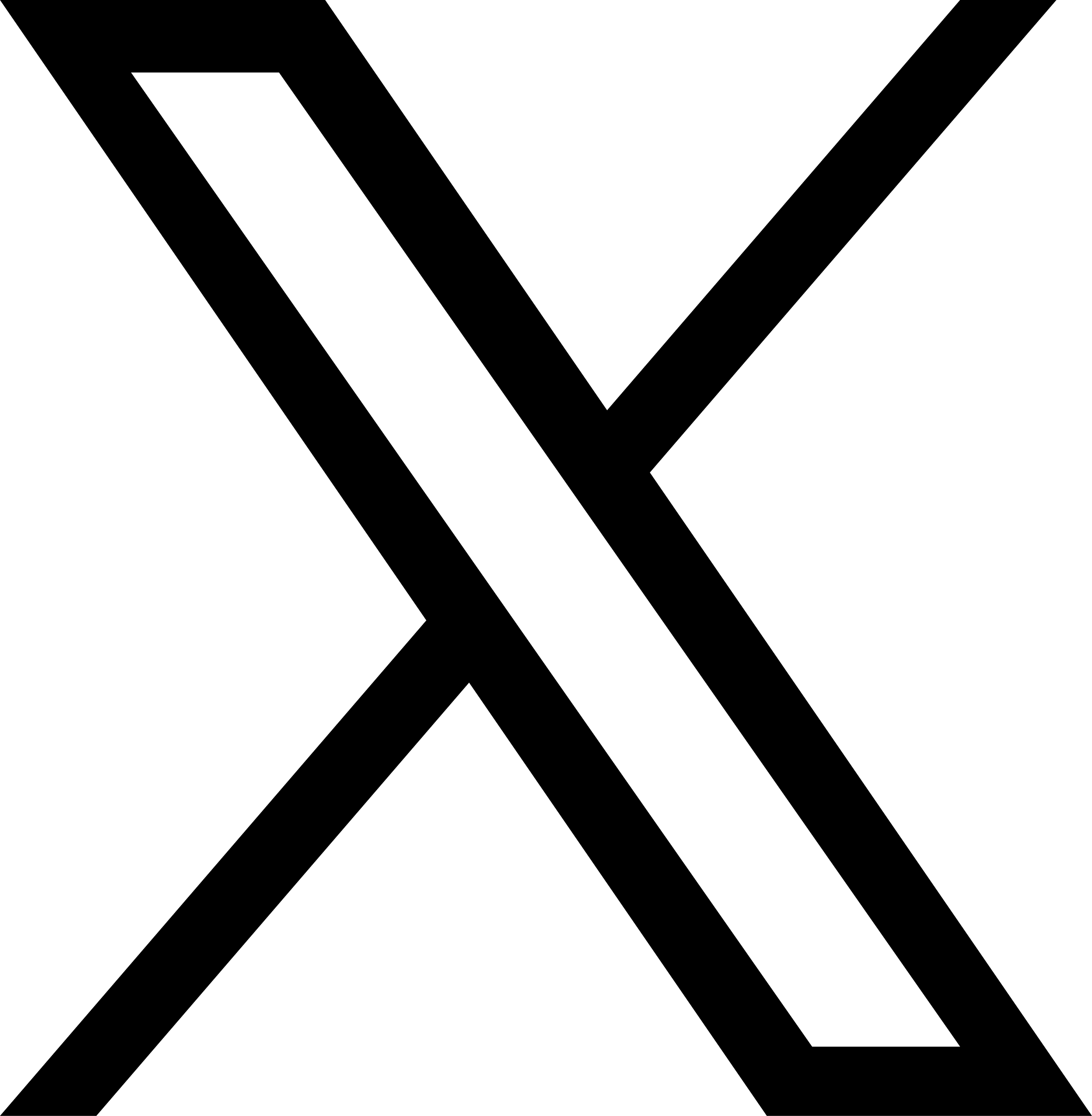海外メンバーとグローバルにビジネスを進める際に求められるのは、どのようなスキルでしょうか。相手とコミュニケーションを取るうえで、当然「語学力」は必要になりますが、それだけでは十分とは言えません。相手の言動の真意を理解し、自分の思いを正しく伝えるためには、相手の持つ「文化」に対する理解が欠かせません。
今回のコラムシリーズ「EATモデルを活用した異文化理解教育」では、グローバルビジネスを円滑に進めるうえで重要となる異文化理解とその教育の実践例をご紹介します。
衰えない日本企業のグローバル志向
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現在も、日本企業のグローバル志向は衰えていません。経済産業省の調査報告[ⅰ]では、「コロナ禍においても企業の海外展開の意欲に変化はない」と述べられており、人口減少に伴う国内需要縮小が確実な中で日本企業が海外に活路を求める姿勢は、コロナ禍でも変わらないということがうかがえます。
こうした状況下で、グローバルビジネスを展開している日本企業において、海外出張者は減り、海外とのWeb会議の機会は増えるという変化が起こっています。つまり、海外に足を運ばずとも「Webでつながる」という形で海外メンバーとビジネスを進めるケースが増えているのです。
異文化理解教育の重要性
海外メンバーとビジネスを進めるうえでは、「文化」の違いに注意する必要があります。たとえば、日本社会でよくみられる「あうんの呼吸」は通用しませんし、「察してもらうこと」を海外メンバーに期待するのもナンセンスでしょう。そこでグローバルビジネスを円滑に進めるために重要となるのが、「異文化理解」です。
「異文化理解力」を向上させるための直接的な方法のひとつは、対象者に留学や海外研修、海外駐在の経験を積ませることです。ただし、この方法のみでは体系的に異文化を理解することは難しいですし、Afterコロナを見据えた海外トレーニー制度の再考【前編】にて解説の通り、研修制度等で海外に派遣する人数は今後厳選されるため、多くの企業にとっては現実的とは言えないでしょう。
前述のような背景から、より現実的な方法として、国内で実施する研修を通じていかに異文化理解力を向上させることができるかに企業の担当者の関心が集まっています。
参加者の腹落ちを促すEATモデル
異文化理解のための研修プログラムをデザインする際、次のような構成が一例として考えられます。

このように、理論の解説から入る研修プログラムの場合、「理論は分かるけれどイメージできない」「言いたいことは分かるが、賛同できない」など、否定的な感情が生まれることがあります。また、ある程度知識を持っている参加者は「言われなくても理論は分かっているので、どう現場で生かすことができるかが知りたい」と感じるかもしれません。こうした否定的な感情が生まれると、参加者は研修内容を受け入れづらくなり、研修効果も残念ながら低くなってしまいます。
そこで、異文化理解教育に限らず、研修を効果的なものにしうる研修デザインの手法の一つとして、「EAT」モデルをご紹介します。EATは、“Experience” “Awareness” “Theory”の頭文字であり、それぞれの意味合いは以下の通りです。

この図表の通り、E→A→Tの順番に研修をデザインした方が、参加者の腹落ち感のある理解につながるというのがEATモデルのポイントです。つまり、理論や理屈を説明する前に、まずは異文化理解のためのケーススタディなどを通じて「経験」し、そこからの「気づき」を促し、最後に「理論」を解説することによって、参加者の理解度も納得感も高まるということです。
EATモデルを体験してもらうには、大きく2つの方法があります。1つ目は研修の場で実際に経験してもらう方法です。たとえば、体験型の演習などを取り入れて、まず参加者に何かしらの経験をしてもらう形が考えられます。
2つ目は、過去の経験を思い出してもらう方法です。以下は2つ目の方法を用いて、前述のプログラム構成をEATモデルでデザインした例となります。

このように、まず自身の経験からスタートすることで、参加者は受け身ではなく、主体的に研修に取り組むようになります。また、参加者同士で話し合った共通項や気づきに対して補足する形で講師が理論の解説を行うと、自分たちが気づかなかった視点なども理解しやすくなり、納得感も高まります。
当社が提供しているグローバルリテラシー研修でも、このEATモデルを活用してプログラムをデザインしています。次回のコラム「EATモデルを活用した異文化理解教育(2) ― ケーススタディの活用事例 ―」では、異文化ケーススタディを活用した実際のプログラム例をご紹介します。
【関連サービス資料】
グローバルリテラシー研修
(参考文献)
中村文子、ボブ・パイク著 「講師・インストラクターハンドブック 効果的な学びをつくる参加者主体の研修デザイン」(2017年)
[ⅰ] 令和2年度 Withコロナ時代における企業の海外ビジネス戦略構築に向けた調査報告書(経済産業省 九州経済産業局)8頁
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。