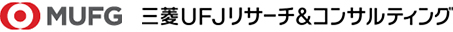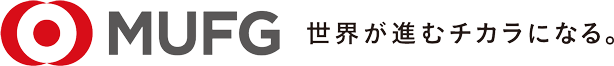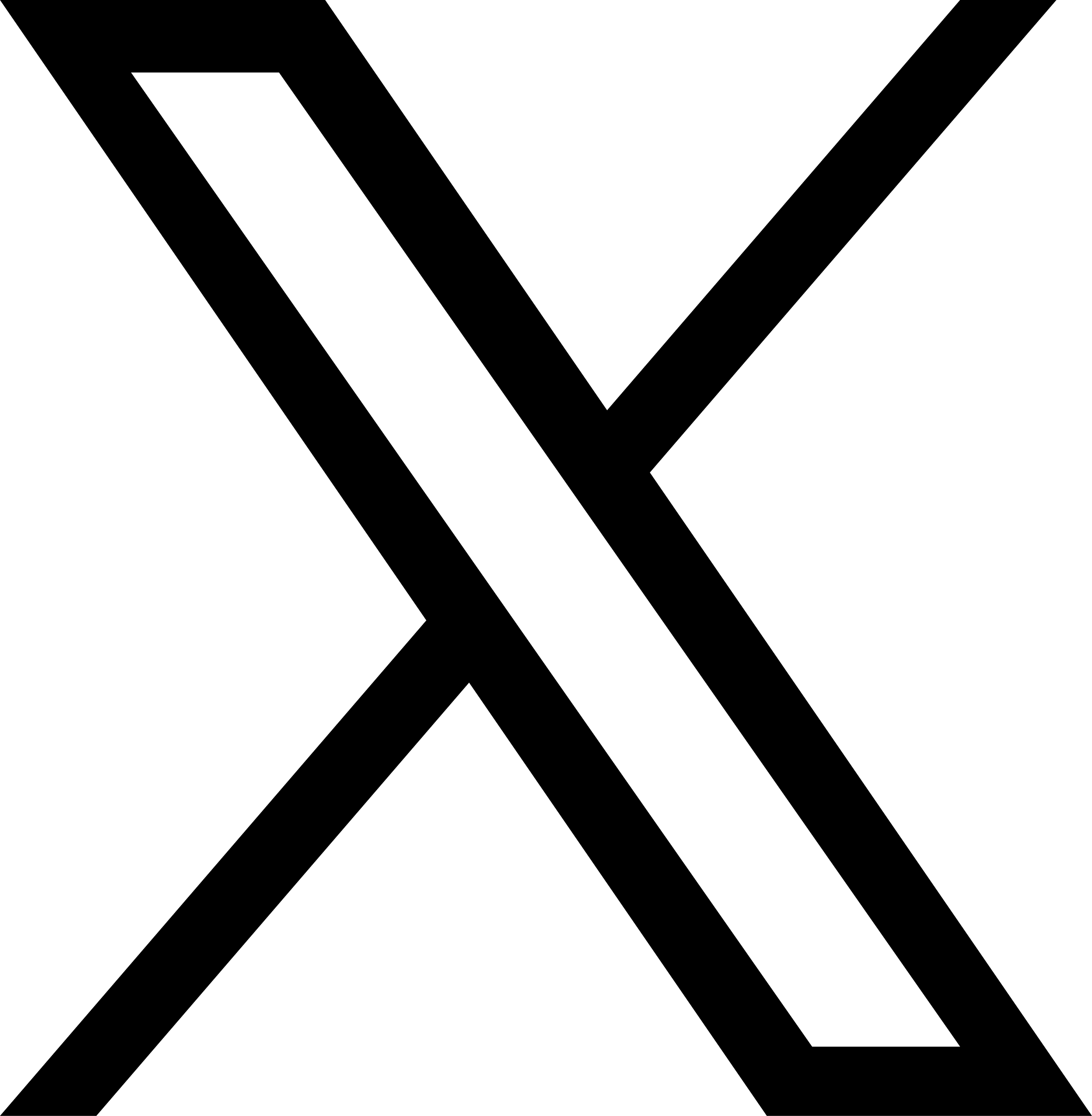人的資本経営を目指す企業では、人材版伊藤レポート2.0[ 1 ]の「人材戦略に求められる3つの視点と5つの共通要素」を踏まえて人材戦略を策定し、企業のあるべき姿の実現に向けた取り組みを進められていることと思います。
当社で人材戦略策定に関するコンサルティングやセミナーを行う中で、人材戦略の中核となる人材ポートフォリオの議論になると、ご意見・ご質問が具体的かつ活発になる傾向を感じます。これは、多くの企業が苦労していることの表れとも考えられます。人材ポートフォリオの策定は、人材戦略策定プロセスにおける重要な論点でありながら、その着手や検討が難しいテーマといえるでしょう。
そこで本コラムでは、事例を交えながら経営戦略と人材戦略を連動させる「動的」な人材ポートフォリオ策定のポイントについてご紹介します。
「動的」な人材ポートフォリオとは
人材ポートフォリオとは、経営戦略を実現するために必要な人材の質(どのようなスキルを持つ人材か)と量(どれだけの人数が必要か)を整理したものです。人材ポートフォリオは一度整理すれば終わりというものではなく「動的」であり、かつ、可能な限り定量的に示すことが重要です。
「動的」とは、人材の質・量における「To-Be(あるべき姿)」を、経営環境や状況の変化に応じて、適宜ローリング(再設定)できる状態を指します。例えば、人材獲得のための採用や育成が計画通りに進んでいない場合は、直接雇用に代えて外部委託を活用するなど、状況に応じた方針の切り替えが想定されます。このように、状況の変化に応じて人材ポートフォリオも更新し続ける必要があるのです。
また、人材ポートフォリオは定量的に表現することで、「As-is(現状)」を客観的かつ正確に把握し、「To-Be(あるべき姿)」を具体的に定義できるため、関係者間の共通認識も形成されやすくなります。ただし、これまで人事情報を一元化・可視化していない企業では、一気に全てを数値化するのは困難です。その場合であっても、「動的」な人材ポートフォリオとするためには、人材の質・量のうち、量は少なくとも想定される変動状況(増加・減少・現状維持)までは定めておくことが肝要です。
事例を通して、「動的」な人材ポートフォリオを考える
ここでは、 “「動的」な人材ポートフォリオ”の解像度を上げるため、コンサルティング事例をベースとしたサンプル事例をご紹介します。
例えば、「今後10年で既存事業を徐々に縮小させると同時に、ようやく形になってきた新規事業を拡大し自社の柱とする」という経営戦略を持つ企業の場合、どのような人材ポートフォリオを策定すべきでしょうか。なお、現在の既存事業を担っている人材は、主に製造技能職や事務職だと仮定します。
まず、新規事業を強化するには、新規事業とする領域の専門人材が必要となります。この際、その人材要件(どのような能力や経験を持つ人材か)と、10年後までに何人(ボリューム)の確保を目指すべきか検討します。この時、人事情報の一元化・可視化がなされているかどうか、経営戦略を踏まえた要員計画の有無によって、10年後の目指す姿の定量化のレベル(具体的な必要人数まで設定できるか、増加・減少・現状維持などの変動状況までか)は変わります。そして、要件を満たす人材が自社に存在しない場合は、新規採用や経験者採用での獲得、あるいは、業務委託による獲得が選択肢として浮上します。
一方、持続可能な経営のためには、既存事業に従事する人材についても、ビジネスの状況に合わせた「削減」または「変化」という調整が必要となります。「削減」の場合、現在および未来の人員構成(年齢分布)を踏まえた上で今後の増員を控えるといった緩やかな対応から、早期退職の実施も含めた判断の検討まで考えられます。「変化」であれば、10年後までに基幹職や新規事業の領域における専門人材にシフトさせる、さらには既存事業ごとM&Aで切り離すといった大胆な選択肢も含め、講ずべき打ち手はさまざまです。
しかし、新規事業はその性質上、不確実性が高く、流動性があることも十分に想定されます。よって、現時点で新規事業に関わる人材の質・量について具体的・定量的に10年後を描くことは現実的ではありません。また、数年後と10年後では人材ポートフォリオが大きく異なることも考えられます。
実際に、この事例と類似した状況にあった企業を支援した際には、10年後のあるべき姿を示した「人材ポートフォリオ(最終理想形)」と、中期経営計画と連動させ、まずは3年後にどのような状態になっているべきかを示した「人材ポートフォリオ(第1段階)」の2パターンの人材ポートフォリオを策定しました。このアプローチにより、10年後を見据えながら、最初の3年間で達成すべき具体的な状態や取り組み事項が明確になり、現実的で実効性のある、すなわち「地に足の着いた、実のある」ロードマップを作成できました。なお、この企業では現在、ロードマップに基づいて最初の1年が経過しようとしていますが、新規事業の領域における専門人材の早期獲得や将来に向けた安定的な社内体制の構築が進んでいます。その一環として、専門職コース(人事制度・教育制度)の見直しを推進していますが、全経営層・現場責任者も巻き込んで人材戦略を策定したことで、現場の協力を得やすくなっています。また、この1年で新規事業領域の専門人材の獲得について、「特に重要な3職種に絞って強化する」「職種を絞り、定義を明確にしたところ、既に該当する自社社員が数名いる」「自社に合ったスピード感・柔軟性が求められるため外部委託は考えられず、社内からの人材育成を最重要視する」という方針や事実が明確になってきました。これらにより、10年後の「人材ポートフォリオ(最終理想形)」の新規事業領域の専門人材の質と量が見直され、それを満たすための獲得方法が変更されています。まさに「動的」な人材ポートフォリオの特長が生かされている事例です。
「動的」な人材ポートフォリオ策定を通して自社のあるべき姿について対話することから始める
不確実性の高い事業環境では、人材ポートフォリオ策定の難しさを感じ、なかなか着手しづらいかもしれません。しかし、事例が示すように、最終的なゴールを視野に入れながらも、まずは具体的に描ける中間ゴールに向けて取り組むことが効果的です。そして、その中間ゴールに向けて行動しながら、最終ゴール自体も自社にとってよりよいあるべき姿に適宜変化させていくという運用が、「動的」な人材ポートフォリオの要点と考えます。
既に人材ポートフォリオを策定済みの企業でも、これまでの取り組みを改めて振り返り、得られた結果と目指す姿とのギャップを洗い出すことが重要です。その上で、目指す姿【To-Be(あるべき姿)の人材ポートフォリオ】の変更が必要か、関係者間で共有・議論されることをおすすめします。
「動的」な人材ポートフォリオ策定や、現在の人材ポートフォリオの見直しを通じて、自社のあるべき姿について対話を深め、最適な形を模索し、人的資本経営を深化させましょう。
【関連サービス】
人的資本の測定・開示/人的資本経営の実践
【関連資料】
【資料ダウンロード】『人的資本経営・開示に関するコンサルティングメニュー』のご紹介
【関連レポート・コラム】
事業戦略と連動した人材ポートフォリオの考え方
人的資本経営に向けた人材戦略策定・可視化のポイント~人材戦略の定義と効果的な策定プロセスとは~
人的資本KPIマネジメント実践のポイント
人的資本経営~伊藤レポート2.0から考える人的資本開示のポイント~
[ 1 ]経済産業省「人的資本経営」https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html(最終確認日:2025/1/18)
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。