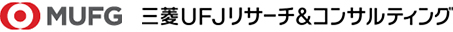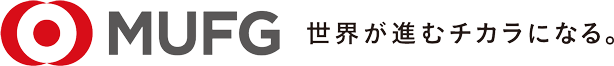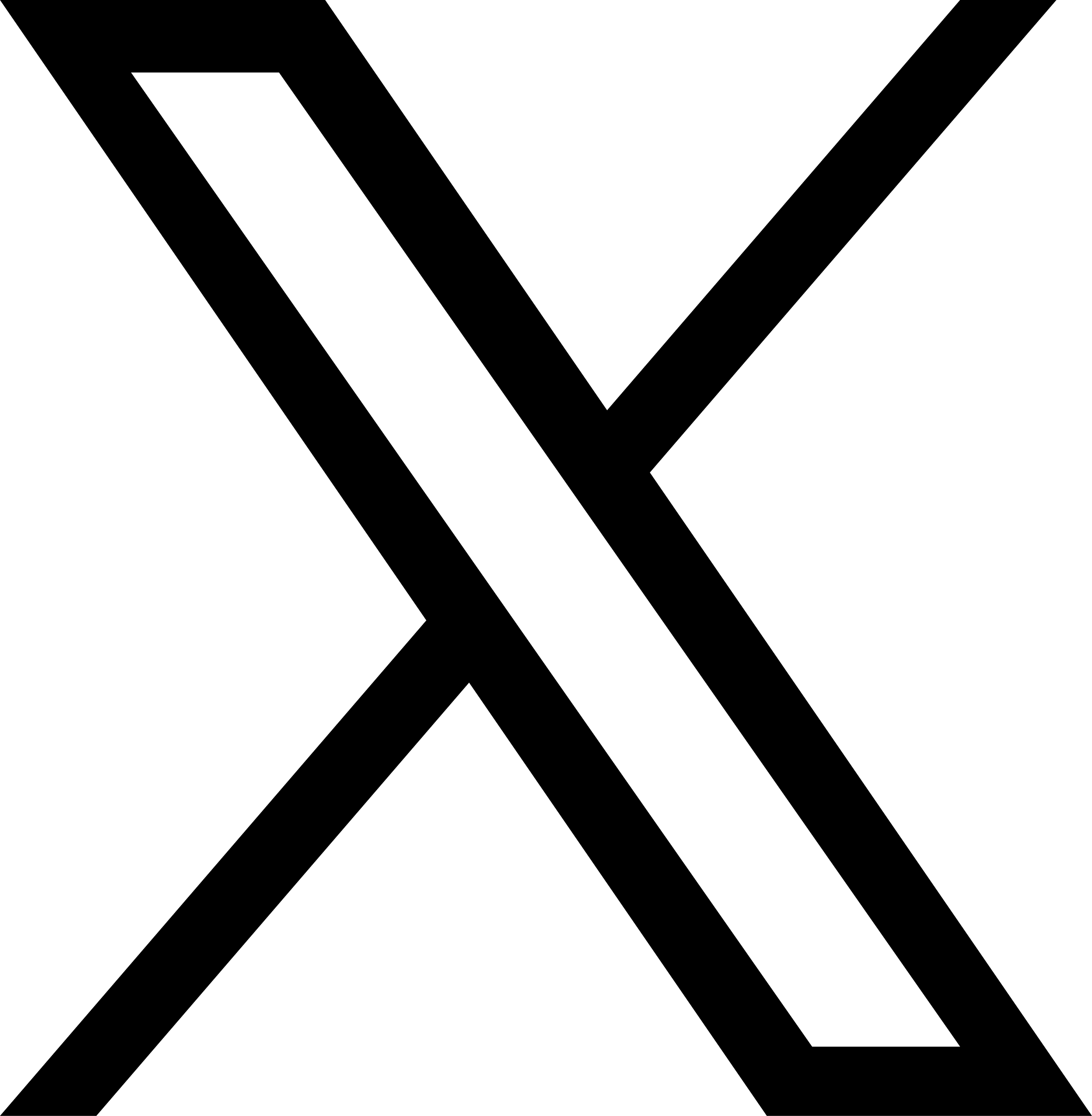近年、自治体が総合計画を策定する際に、策定過程に住民参加の仕組みを組み込むケースが多くなっている。素案がまとまった段階でこれを住民に公表して意見を募り、計画に反映していくといった間接的な参加機会は従来から広く普及していたが、近年は素案をまとめるまでの策定プロセスに住民が直接参加できる機会を設ける例が増えている。
こうした仕組みの代表的な例が、住民参加によるワークショップ等の検討組織を設けて提言を策定し、これを新しい総合計画に反映するという手法である。こうした手法を本格的に導入したのは、東京都三鷹市がその草分けであると言われる。三鷹市では、2001年の新しい総合計画の策定に際して、公募市民による「みたか市民プラン21会議」を設置し、最終的には300人を超える市民が2年間にわたって検討を重ね、提言書を市に提出した。当時は極めて先進的な事例として注目された取組であるが、現在では同様の住民による提言組織を設置する例は決して珍しいものではなくなっている。
こうした参加機会を設ける利点は、住民のニーズを直接的かつ具体的に総合計画に反映することが可能になるという点である。近年では、単なる意見や要望の域を超え、新しい総合計画に盛り込むべき施策や事業を体系的に示すような本格的な提言書が成果として提示される例も増えており、こうした事例では住民の提案が新しい総合計画のたたき台として扱われ、その内容がそのまま行政の総合計画にも反映される部分も多くなっている。また、策定プロセスに参加し、実際に自分たちの意見が反映されるという経験によって、住民に自治体行政への当事者意識が芽生え、住民と行政との総合計画の共有化も促進される。さらに、職員の側にもこうした経験を通じて、政策の立案や施策、事業の実施に際しての住民との連携・協力に対する意識が醸成される。
一方、策定プロセスへの住民参加には課題も少なくない。まず、世代や立場など属性が全く異なる住民が集まって議論し、意見を一つの提言にまとめ上げることが困難である点である。このため、検討に非常に多くの時間を要するのが一般的であり、前述の「みたか市民プラン21会議」でも実に延べ773回の会議や打ち合わせが実施されている。しかし、他に本業をもつ一般の住民が高頻度の会議に参加することは困難であり、その後の類似の取組においても、同様の頻度で会議が開催された例はあまり見られない。そこで、専門家による支援など少しでも円滑に検討が進められるように行政のサポートが必要になるが、あまり行政主導で会議を進めると住民主体という検討組織の趣旨を損なうこととなる。
また、一般に検討組織の規模は住民全体から見れば一部であり、多忙な属性の住民の参加は少なくなるため属性も偏っている場合が多い。このため、別途アンケート調査などで住民全体の意向を把握し、これを踏まえて検討することが必要である。
さらに、これが最も重要なことであるが、住民の提言のすべてをそのまま総合計画に反映すれば良いというわけではない。財源や制度面、関係主体との調整といった実務的制約により、最終的に総合計画に反映できない施策や事業も当然出てくる。このため、こうした制約と調整の必要性についてあらかじめ住民に説明し理解を得ておくことが重要となる。
自治体総合計画策定プロセスへの住民参加を実りの多いものとするためには、行政、住民双方が、これを単に住民の意見を汲み上げる機会と捉えるのではなく、与えられた制約の中で、住民と行政がより良い政策を作り上げるために知恵を出し合う場として捉える意識を持つことが強く求められる
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。