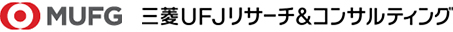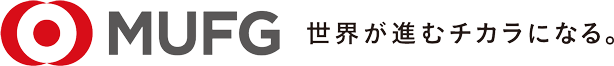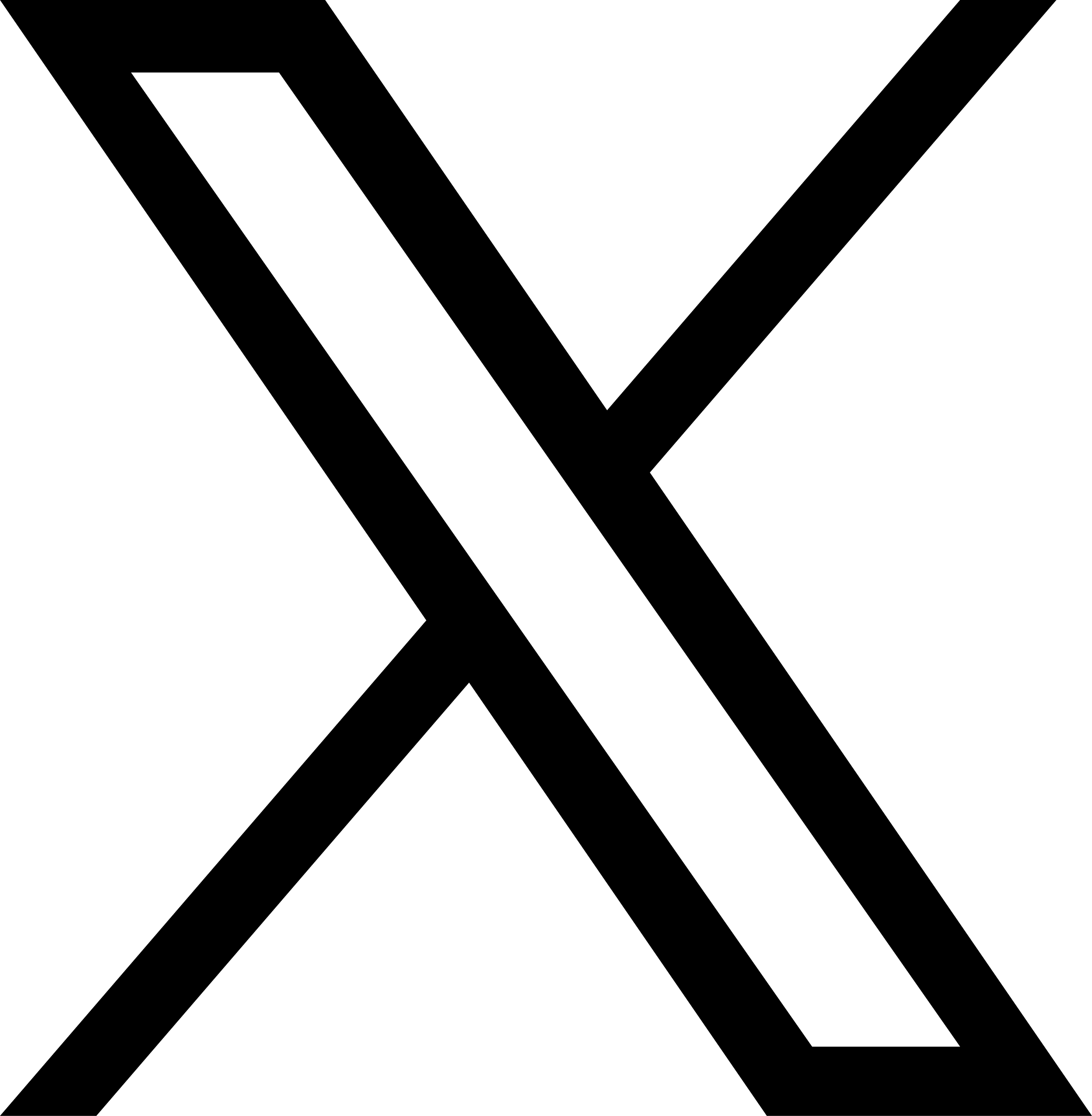航空政策がにわかに脚光を浴びている。昨年5月の「アジア・ゲートウェイ構想」では「航空自由化」(アジア・オープンスカイ)が打ち出され、今春には航空法改正に際し、空港会社やターミナル会社への「外資規制」の是非が大きな社会的関心を集めた。
航空自由化は、交通政策審議会航空分科会答申「戦略的新航空ビジョン」にそのまま採り入れられ、航空政策は大転換することとなった。これまで国際航空輸送においては、二国間協定により事業会社、乗入地点、便数が取り決められていたが、今後は「国際的に遜色のない航空自由化(アジア・オープンスカイ)を、スピード感を持って戦略的に推進する」こととなった。
こうした政策転換の背景には、米国・EU間をはじめ、航空自由化が世界的な潮流になっていることに加え、仁川、香港、上海等に巨大空港が建設され、わが国がアジアの国際航空ネットワークから取り残されるのではないか、との危惧がある。
アジアの追い上げに伴うわが国の競争力強化という構図には、1995年1月の阪神・淡路大震災で神戸港が壊滅的な被害を受けた際、いわゆる「ハブ機能」の低下が大きな社会的関心を集めた海運・港湾分野と相通じるものがある。残念ながら、わが国の港湾は、香港、上海、釜山等に大きく水をあけられたままの状況にあるが、その経験は航空・空港分野にも活かせるのではないか。
国際的な競争環境に関して、航空・空港と海運・港湾の間で最も異なる点は、国際航空では二国間協定により事業会社、乗入地点、便数が制約されてきたのに対し、外航海運では早くから主要海運国により「海運自由の原則」が確立され、海運会社の国籍を問わず自由に国際航路が開設できる点である。
このため、外航海運企業では経営のグローバル化が非常に進んでいる。わが国の主要海運会社では、船舶の多くがパナマ、リベリアなどの外国船籍であり、船長を除く乗組員の多くが外国人である。さらにはアジア全域の統括機能を日本でなく香港に置いている例もある。わが国の外航海運業界は幾度かの再編を経て大手3社グループに集約されたが、3社は世界大手の一角としての地位を維持している(米国では外国資本による合併・買収により大手海運企業が消滅した)。一方で、全国の港湾のコンテナ取扱量をすべて合わせても、香港や上海1港に及ばないなど、わが国の港湾の地盤沈下は著しく、その要因の1つに、政策転換に時間をかけすぎたことが挙げられる(2007.1.9付本欄参照、https://www.murc.jp/library/column/sn_070109/)。
航空・空港分野はどうか。空港についてみると、国際旅客・貨物取扱量でわが国の過半を担う成田空港は、東アジアでも長らく香港に次ぐ地位を占めてきたが、2006年には国際貨物取扱量で仁川に逆転され、上海・浦東にも急追されている。何より首都圏空港(成田、羽田)は発着枠に余裕がないため、航空自由化の検討が先送りされている。一方、わが国の航空業界は大手2社グループにほぼ集約されたが、十分な国際競争力を持っているとは言い難い状況である。
こうした中でわが国は航空自由化に舵を切った。これは企業間の競争促進が航空市場全体を効率化させ、その効果が利用者に還元されるという考え方に立っている。しかし、市場に委ねるということは、米国の海運の例のように、わが国の航空企業が消滅してしまう可能性もはらんでいる。また、わが国の空港は、港湾と比較すればアジアの中で大きな存在感を維持しているが、今後は予断を許さない。
わが国の航空行政は、利用者便益、航空関連産業の競争力、空港の競争力を高い次元でバランスしていくことを目指している。ただし、そのためには港湾の例に見るとおり「スピード感」がとりわけ重要である。三兎を追って一兎をも得ず、ということがあってはならない。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。