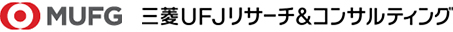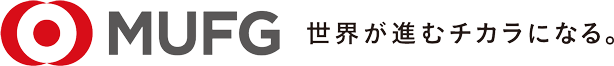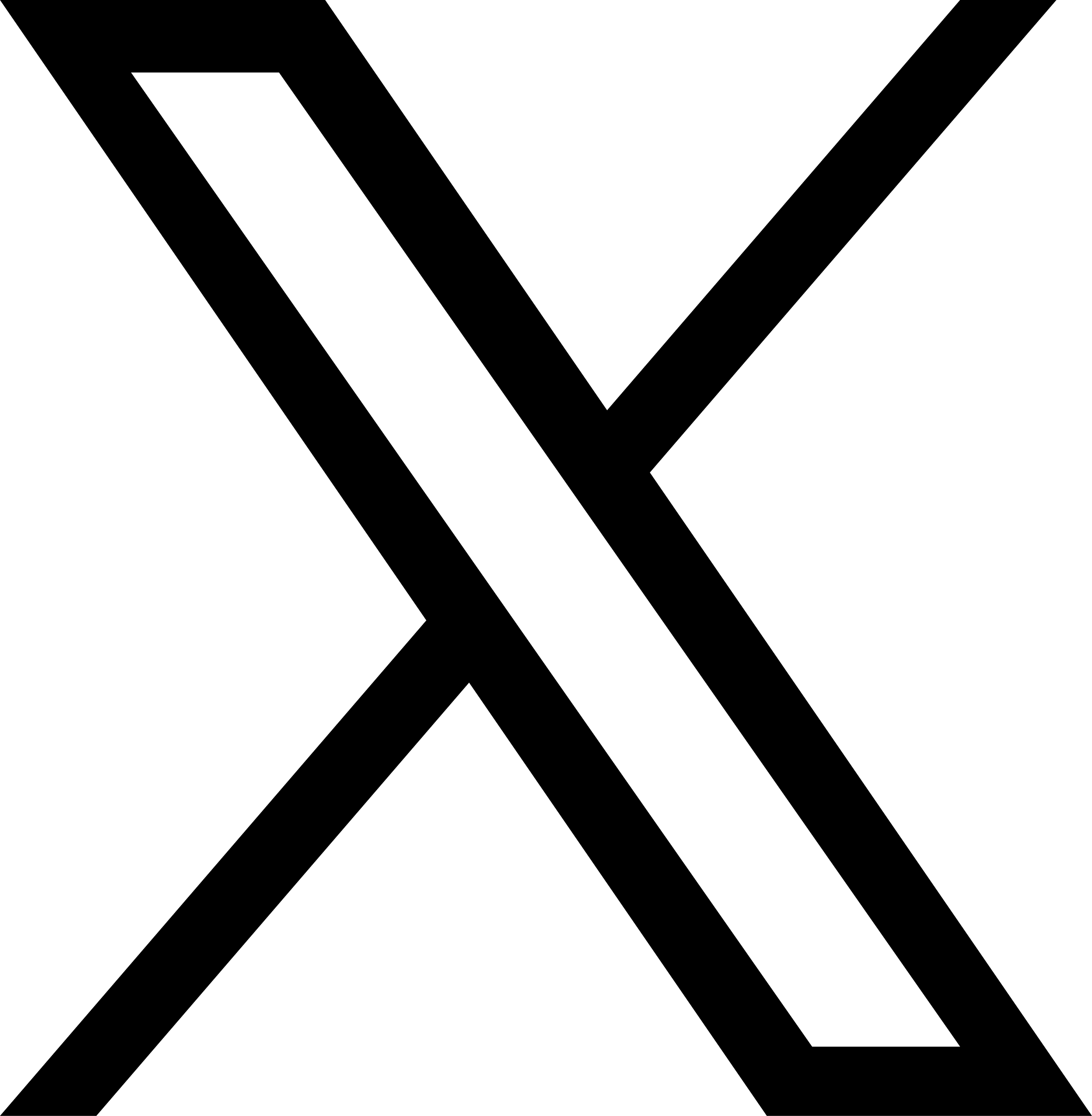失敗が相次ぐ私立大学の資産運用
駒澤大学(2008年11月19日報道、154億円の実現損失)、立正大学(11月21日報道、148億円の含み損失)と、相次いで私立大学の資産運用に関する失敗が表面化している。金融危機の広がりを示す一例として受け止められることも多いが、各大学における運用プロセスの欠陥も無視できない。
報道によれば、駒澤大学が損失を計上したのはデリバティブ契約(最低3社の外資系金融機関と契約していた金利スワップと通貨スワップ)の解約損失だという。読売新聞(12月21日)によれば、『駒大では大学の財産を「確実な有価証券」や「確実な銀行の定期預金」で理事長が保管すると規定し』た上で、当該デリバティブ契約は財務担当者が捺印の上で承認を申請し、理事長がこれを(担当者を信頼していたので特段の説明も求めずに)決裁することによって実行された模様である。規定が定めていた「財産の保管」の範囲からデリバティブ契約が外れていたのか、理事長の裁量権が規定よりも上位に存在していたのか、何れにしてもプロセス設計上の重大な欠陥といわざるをえない。
立正大学の場合には、仕組債が評価損の主因のようである。仕組債の発行体は格付が高い優良機関が多く、例えば元本が円建でさえあれば「確実な有価証券」とみなされてしまっているケースもあると思われるが、これは実は「あらかじめデリバティブ契約をセットにした債券」と評価すべき経済的性質をもっていることが多い。立正大学の運用方針がどのようなものかは不明だが、『株への投資を禁止し、投資信託などをすべて円建てにしている(同じく読売新聞12月21日)』という内部指針と比較すれば明らかに違和感のある商品への投資を行っている点、やはりプロセス設計上の重大な欠陥が存在している可能性を示唆している。
本稿では、何もひたすらリスク回避を追及するために、担当者の判断の余地が一切なくなるほどの厳格で保守的な規定・手続きを整えてしまうことを推奨しているわけではない。我々の実際のコンサルティングにおいても、学校法人の意図・体制によってはデリバティブの活用は選択肢の一つである。しかし今回公となった損失の規模やその後の対策をみるに、投資の時点で「本来の意図とは異なる」判断を下していたことは明白で、かなり初歩的な部類の失敗と評価している。
今回の件から得られる教訓として、(1)「確実な」といったあいまいな修飾語には実際上の効果はない、(2)申請書・印鑑によって個人責任を明確にしていても損失の回避・回復には役立たない、(3)運用対象は明確でなければ意味がないし、対象分類が大まかに過ぎると実効性に欠ける、(4)取引金融機関を複数にしても相互牽制は期待できない、といったあたりは銘記しておきたい。市場環境を考えれば、両大学に限らず損失を抱えている学校法人は多数に及ぶものと想定される。一度失敗を報じられたならば、その法人はいわば弱点を周知されたも同然であり、適切な第三者による早急な検証と運用プロセスの見直しが不可欠であろう。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。