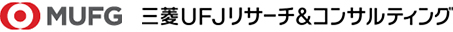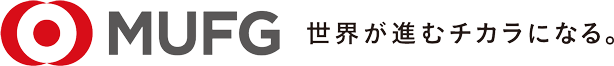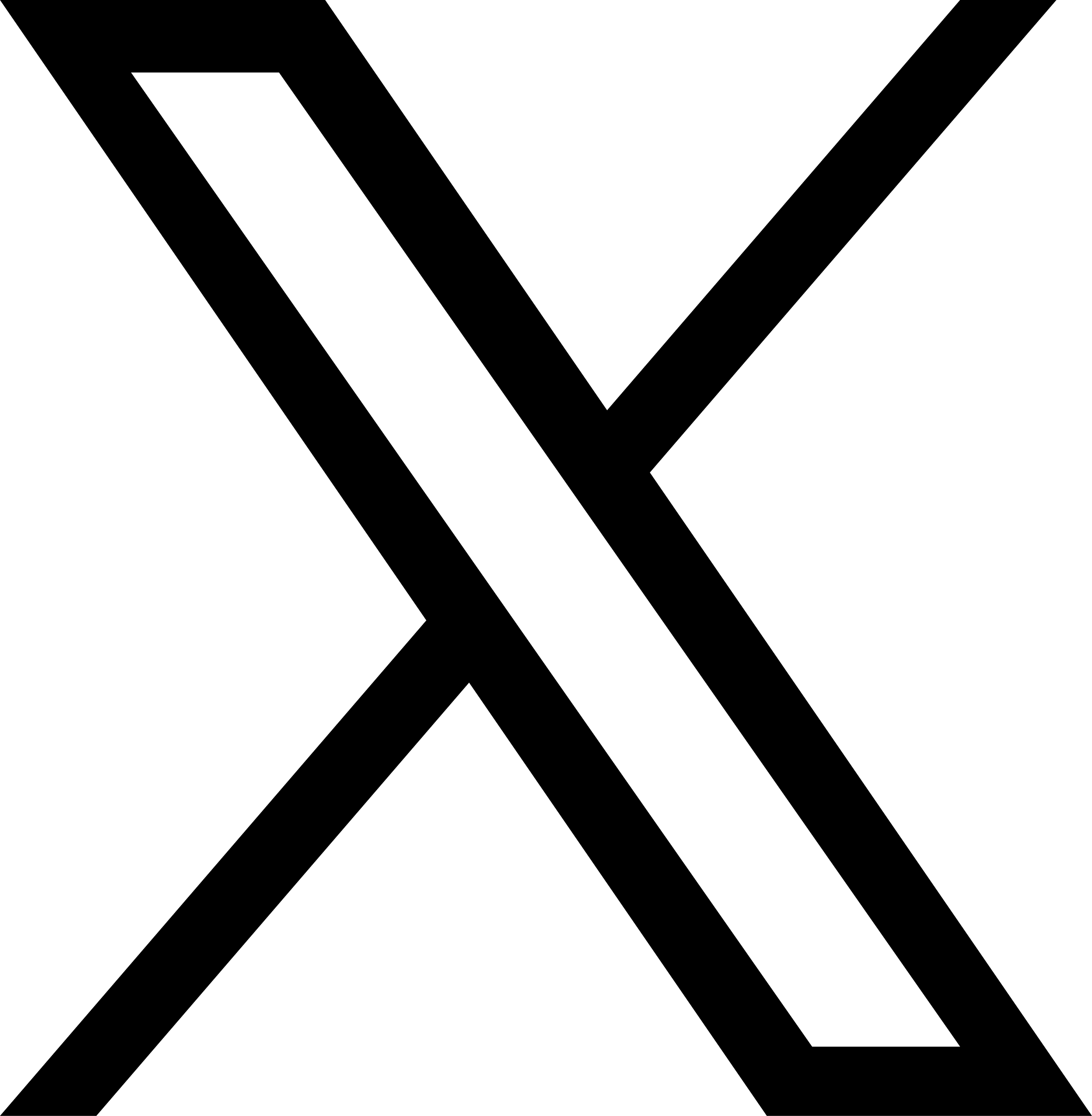科学技術立国政策の下,研究開発に対する公的資金配分は2002年度までの10年間で約1.7倍の約3兆5,444億円に増加し,その後も毎年度,概ね3兆5千億円強で推移してきた(文部科学省)。加えてここ数年は大型の補正予算が組まれており,補正予算を含めた政府の科学技術関係経費は,2008年度は約3兆7,955億円(内閣府,2008),2009年度に至っては経済対策も加わり約4兆9千億円にも上っている(文科省,2009)。さらに、この政府の科学技術関係経費とは別に,地方自治体における科学技術関係経費が毎年度4千億円強ある(内閣府)。
 図 1 政府の科学技術関係経費の推移
図 1 政府の科学技術関係経費の推移
2008年度は内閣府(科学技術政策・イノベーション担当)「平成21年度科学技術関係予算案について」 (2008年12月26日)。
2009年度は文部科学省「平成21年度補正予算案における科学技術関係経費(速報値)」(2009年5月13日)。
(注1) 各年度とも当初予算額。2009年度のみ予算案の速報値。
(注2) 科学技術基本計画(第1期~第3期)の策定に伴い,1996・2001・2006年度に対象経費の範囲が見直されている。
このように過去約15年間,重点的に予算が配分されてきている公的研究資金は,有効に使われてこそ効果が出るものである。
ところが,短期間に数兆円規模に急拡大したその陰で不正使用が明るみに出るようになり,公的研究資金が有効活用されていないのではないかとの疑問が生じるようになった。こうした状況に対処するため,政府は,研究資金の《「不合理な重複」及び「過度な集中」を排除》する方針を打ち出した(競争的資金に関する関係府省連絡会,2005)がその結果,単純に「重複」を避ける傾向がみられるようになった。「重複」「集中」が公的研究資金の不正使用の温床であり,排除すべきだとの論調も,これに拍車を掛けている。
この現状に対し,筆者は、公的研究資金が有効に活用されていない事例があるのは,単純に「重複」「集中」している状態が原因なのではなく,その「重複」「集中」が”無意識”に生じているためではないかとの仮説を立て調査研究(注1) をおこなった。同じように様々な制度から「重複」して多額の資金を「集中」的に受給していても,成果が上がっている研究課題とそうでない研究課題がある。すなわち,重要な研究課題に”意識的”に「重複」「集中」を図ることは,効率的かつ有効なケースもあるとの考えである。以下,そのポイントを紹介する。
”無意識”な「重複」「集中」はなぜ起こるのか。それは,公的研究資金を配分された研究課題の成果に関する評価(注1) 結果が,公的研究資金の配分審査段階にフィードバックされておらず,活用されていないためと考えられる。
この背景には,評価システムの問題,評価と配分審査のリンケージの問題,配分審査の体制の問題の3つの問題がある。
- 評価システムの問題--公的研究資金を配分された研究課題に対して,次の公的研究資金の配分審査に活用できるような評価項目や評価者による評価が行われていないのではないか。
- 評価と配分審査のリンケージの問題--公的研究資金を配分された研究課題に対する評価結果が,次の公的研究資金の配分審査段階にフィードバックされる仕組みが無いのではないか。
- 配分審査の体制の問題--公的研究資金を配分された研究課題に対する評価結果を次の公的研究資金の配分審査に活かすことができる人材が配分審査をしていないのではないか。
以上のような3つの問題を解決して”無意識”な「重複」「集中」をなくし,公的研究資金のより一層の有効活用につなげるための方策を、続きのコラム「公的研究資金が有効に使われるためには(その2)」で提案する。
(注1) 詳細は、拙著「研究開発に対する日本の公的支援制度の特性と課題~公的研究資金の有効利用のために~」『季刊 政策・経営研究』2009 vol.3(通巻第11号)を参照。
(注2) ここでは正確には「事後評価」を指している。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。