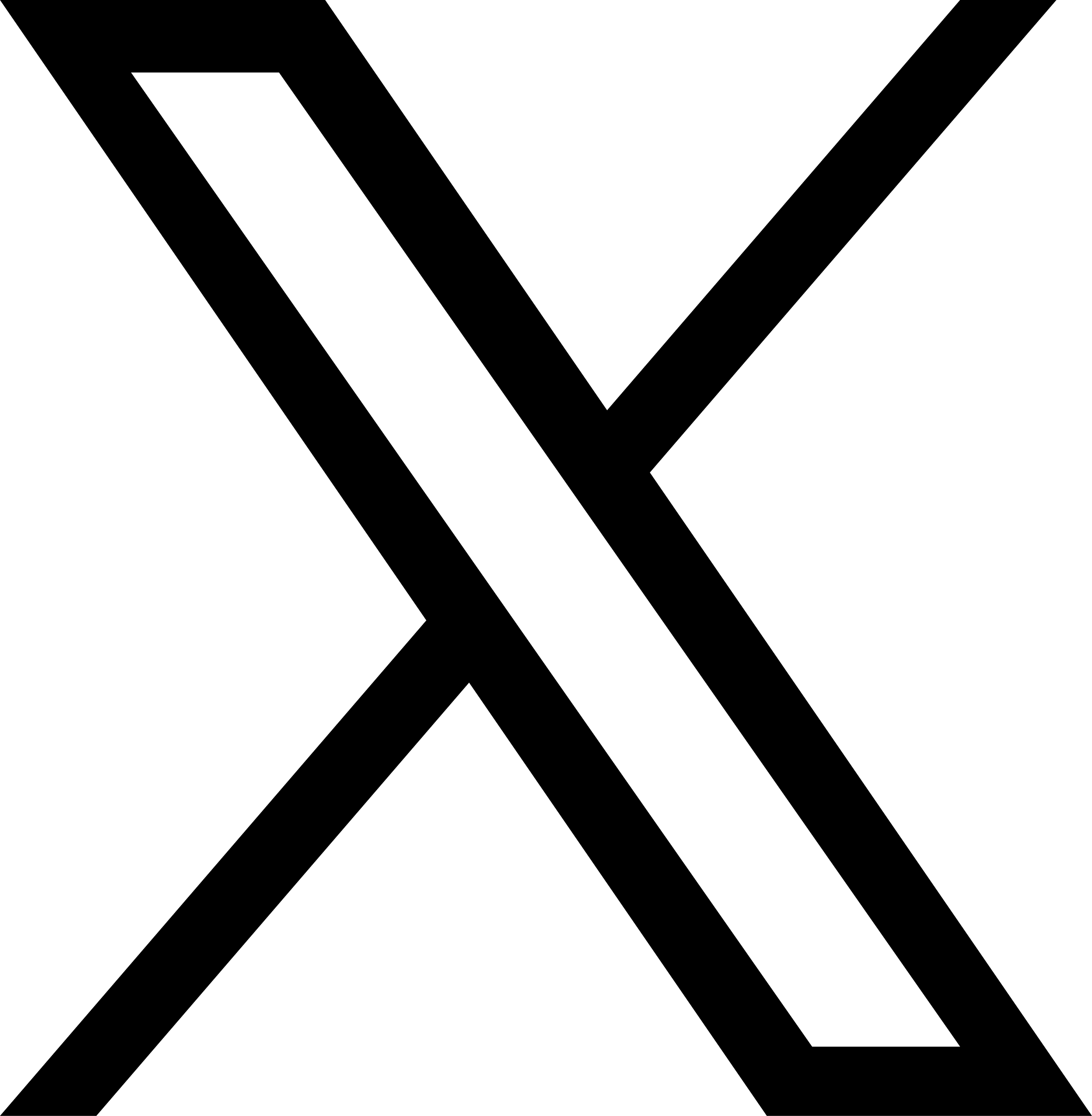はじめに
食卓に並ぶ料理のカロリー計算や栄養バランスの良い献立の作成等、「食の数値化」は、食が身体へ与える影響を事前に予測・計画する手段として、我々の食生活一般に浸透しているように思われる。
他方、食の豊かさを考えるためには、食の「美味しさ」といった感性的な側面にも目を向けることが有益と考えられる。感性的な「美味しさ」を数値化することができれば、アレルギーや宗教上の制約等により摂取できない場合にも、感性的に近しい数値の(「美味しさ」の近しい)食物で代替し、食本来のもつ豊かさをより多くの人が享受できるようになるだろう。例えば、卵やピーナッツ、トマトなどの食材を用いたメニューの魅力を、食物アレルギーのため食べられない人に提供できるようになり、食が本来有する豊かさを共有することができる新たな食生活、価値観を生み出すことができるかもしれない。
食の「美味しさ」の数値化
人は、食の「美味しさ」を、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を通じて得られた情報を脳で総合し、個人の主観に基づく感覚的な判断を下している。このため、人の五感で得た時点での情報には個人差は少ないものの、過去の食体験や嗜好性、社会・文化的差異により培われた「美味しさ」に対する主観的評価には大きな個人差があるため、五感の情報を総合して、最終的に脳が評価する美味しさは個々人で異なってくる。

図1.人が「美味しさ」を感じるまで
本稿では、この五感の中の「味覚」にスポットを当ててみようと思う。味覚が「美味しさ」を判断する上での中心的役割を担っているであろうことは、サプリメント錠剤や機能性食品であっても、味や風味付けを行っていることから考えても、あまり想像に難くないことと思う。
なお本稿では、五感で感じる味を「絶対的な味」、脳で感じる味・美味しさを「相対的な味」と呼ぶ(図1参照)。
味覚とは何か?
本年7月、米国パデュー大学が第六の基本味として脂味「オレオガスタス(oleogustus)」の存在を実験的に確認した論文を発表した(注2)。これまで人間は、苦味、甘味、酸味、塩味、うま味の五つの『基本味』の組み合わせで味を感知していると言われていたが、この発表で、新たに脂味が第六の『基本味』として加わった。
人が美味しさ(相対的な味)を感じるメカニズムは、まず舌に点在する味蕾(みらい)中に50~100個程度あるといわれる味細胞の受容体が、食物中の特定たんぱく質と結合することで、味蕾から脳にシグナルが送られる。この味蕾中の受容体の種類は1,000種類程度あると考えられており、酸味を除く4種類の基本味を構成するたんぱく質の多くについては、既に特定されているという。この受容体を電極に付着させた、たんぱく質検出センサーの開発が進められている。
絶対的な味は数値化可能か?
東京都市大学工学部 平田 孝道 教授は、半導体技術を活用し、食物中に存在する特定のたんぱく質の有無により、電気信号が変化する手のひらサイズのセンサー開発を進めている。このセンサーを活用することで、例えば、給食にアレルギー物質が含まれていないかどうかを検知したり、健康診断における血液検査の分析をその場で実施するような用途が見込まれる。これら用途における技術的障壁はほぼクリアされており、実用化に向けた課題はコストとのことであり、仮にそのバリアが克服されれば、簡便性の良さから一気に普及することが期待される(注3)。
このセンサーをたんぱく質の種類毎に用意し、食物を構成するたんぱく質の種類を全て特定できれば、五感で感じる絶対的な味を数値化できる可能性もある。しかし、このアプローチは、実現に向けた障壁が多いようである。
| 東京都市大学工学部 平田 孝道 教授のインタビュー(1) |
|---|
|

図2.たんぱく質検出センサーを用いた(絶対的な)味の再現
このように、食品・食材に含まれているたんぱく質の「有無(0.1)」を検出することはできるものの、現在のところ、その濃度などの量的な「強さ」までを測定することはできていない。そのため、食品・食材に含まれる個別たんぱく質をセンシングすることから、(絶対的な)味そのものを数値化することは容易ではないとされている。
他方、食品・食材に含まれる個別のたんぱく質ではなく、人の舌を模擬したセンサーにより、苦味・塩味などの基本味の単位(総体・集合)で「強さ」を直接測る技術の開発が行われており(注5)、既に味の“ものさし”として食料品開発等に応用されている。例えば、コーヒー豆のブレンドにおける苦み等の基本味を味覚マップとして数値化しておき、「食材の味の特性」と小売店舗のPOSデータ(消費者の好み)とを組み合わせることで、売上に繋がりやすい基本味の配分を科学的に明らかにすることができる。また、「ウニの味=プリン+醤油」といったように、個別食材の味覚マップの足し合わせにより、味を再現するような応用も可能である。これにより、アレルギーの理由等で特定食材を摂取できない場合にも、絶対的な味を別の食材で代替するレシピが登場する日がくる可能性は高い。
相対的な味は数値化可能か?
食品・食材に含まれる個別のたんぱく質から味の数値化を行うことには依然として技術的な難しさがあるものの、先にみた舌を模擬したセンサーのように、基本味を単位とする絶対的な味についてはある程度数値化できるといえるだろう。では、これで「『美味しさ』を数値化できる」と言えるのだろうか。
先に述べた通り、脳で感じる美味しさ(相対的な味)は五感や過去の食体験等を総動員し、個人の主観により感覚的に判断されるものであり、これを数値化するということは、個人の脳内処理を数値化することを意味する。このため、脳信号を計測・解析することで、美味しさ(相対的な味)を数値化する研究が進められている。
| 東京都市大学工学部 平田 孝道 教授のインタビュー(2) |
|---|
|
食における脳信号解析への期待については、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が本年9月に公表した「第10回科学技術予測調査(注6)」においても言及されている。科学技術予測の側面からも、今後はパーソナルな領域に踏み込んで、相対的な味を数値化していくことが予見されている。
| 「美味しさ」を解明するための今後の研究課題 |
|---|
|
出典:科学技術・学術政策研究所「第10回科学技術予測調査」3.農林水産・食・バイオテクノロジー分野より抜粋
このように、人間の五感レベルの絶対的な味の数値化に加え、脳における判断(相対的な味)の数値化が進むことで、「美味しさ」という感覚的なものを個人レベルで数値化できるようになるだろう。相対的な味の数値化により、個人の主観や感性まで踏み込むことができれば、遺伝情報や行動記録(ライフログ)、世界中にある膨大なレシピデータ等を組み合わせることで、健康、生体、嗜好等の多様な観点から見て個人に最適化された料理レシピを、人工知能が用意してくれる日が来るかもしれない。さらに、3Dプリンターのような製造技術を応用することで、味だけでなく見た目や食感も個人に最適に仕上げた料理ができる可能性もあるだろう。これにより、数値化・データ化された有名レストランの料理を自宅でダウンロードして楽しめるようになったり、記念日等に食べた思い出の味を数十年後に再現できるようになるかもしれない。
数値化の先にある未来
味の数値化に関する技術は、絶対的な味については研究開発が進んできており、今後は、味覚以外の五感を含めて判断する、相対的な味の研究開発が進むことで、人工的な味の再現にまた一歩近づくことができるだろう。これが再現できるようになると、提供する料理のレシピ等、新たな食のオプションを獲得することが期待される。
では、味の数値化により食の豊かさが広がるかというと、必ずしもそうとは言えないのではないか。例えば、複数人で食卓を囲むような場合、会話・コミュニケーションを通じて、他人の「美味しい」という感覚を共有することが、個々人の主観的な判断に何らかの影響を及ぼしうると想定される。誰しも一度は、一人で食べても何も感じなかった料理が、他人の感想・視点が加わることで、「美味しい」という感想に変化する体験をしたことがあるのではないだろうか。こういったシーンや状況に応じて変化する人間の柔軟な感覚を数値化・最適化することは、現在の技術水準では難しい。さらに、食事という卓上の物質に関する科学技術的な研究に留まらず、食卓やそれを取り巻く「場」や「空気」といった、社会学や文化人類学の助けを借りた理解が必要になるだろう。そこには、科学技術による定量化のみでは到達することが難しい、新たな価値観の発見があるかもしれない。
今後、科学技術の発展により、食の数値化・最適化が更に進むことが予見される。しかし、食は栄養摂取等の生理的活動のみならず、食卓における他者とのコミュニケーションといった、社会、文化、精神等の様々な性格を有している。食の豊かさを考えるには、食の需給動向や関連する科学技術の発展のみならず、それに付随する社会、文化、精神等の変化を多面的に捉える必要があるだろう。
(注1)弊社では、自主研究の支援枠組みとして、将来の新しい事業創出をめざした社員の研究・活動に対し投資「インキュベーションファンド」を設けている。本プロジェクトは、同枠組みの助成を受け実施するものである。
(注2)Cordelia A. Running, et al.(2015)Oleogustus: The Unique Taste of Fat, the Chemical Senses article.
(注3)米国国立衛生研究所(NIH:National Institutes of Health)によると、2001~2015年の期間でゲノム解析コストは約7万分の1程度まで加速度的に下がってきている。(参考:NIH「DNA Sequencing Costs」http://www.genome.gov/sequencingcosts/)
(注4)電気信号の強さから階調を表現することも原理的には可能だが、現時点の技術水準では実現できていないとのことである。
(注5)代表的な研究として、九州大学味覚・嗅覚センサ開発センター(センター長 都甲潔氏)が開発する、味細胞を覆う生体膜を模擬した味覚センサーが挙げられる。
(注6)第10回科学技術予測調査:http://www.murc.jp/library/column/sn_150824/
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。
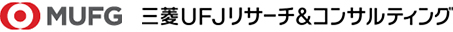
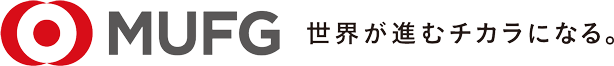

 本稿は、新たなテクノロジーの台頭により、社会の慣習がどのように変化していくのか、「食(つくること/たべること)」を事例に考える社内自主研究
本稿は、新たなテクノロジーの台頭により、社会の慣習がどのように変化していくのか、「食(つくること/たべること)」を事例に考える社内自主研究