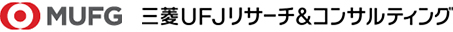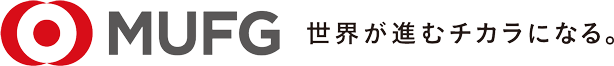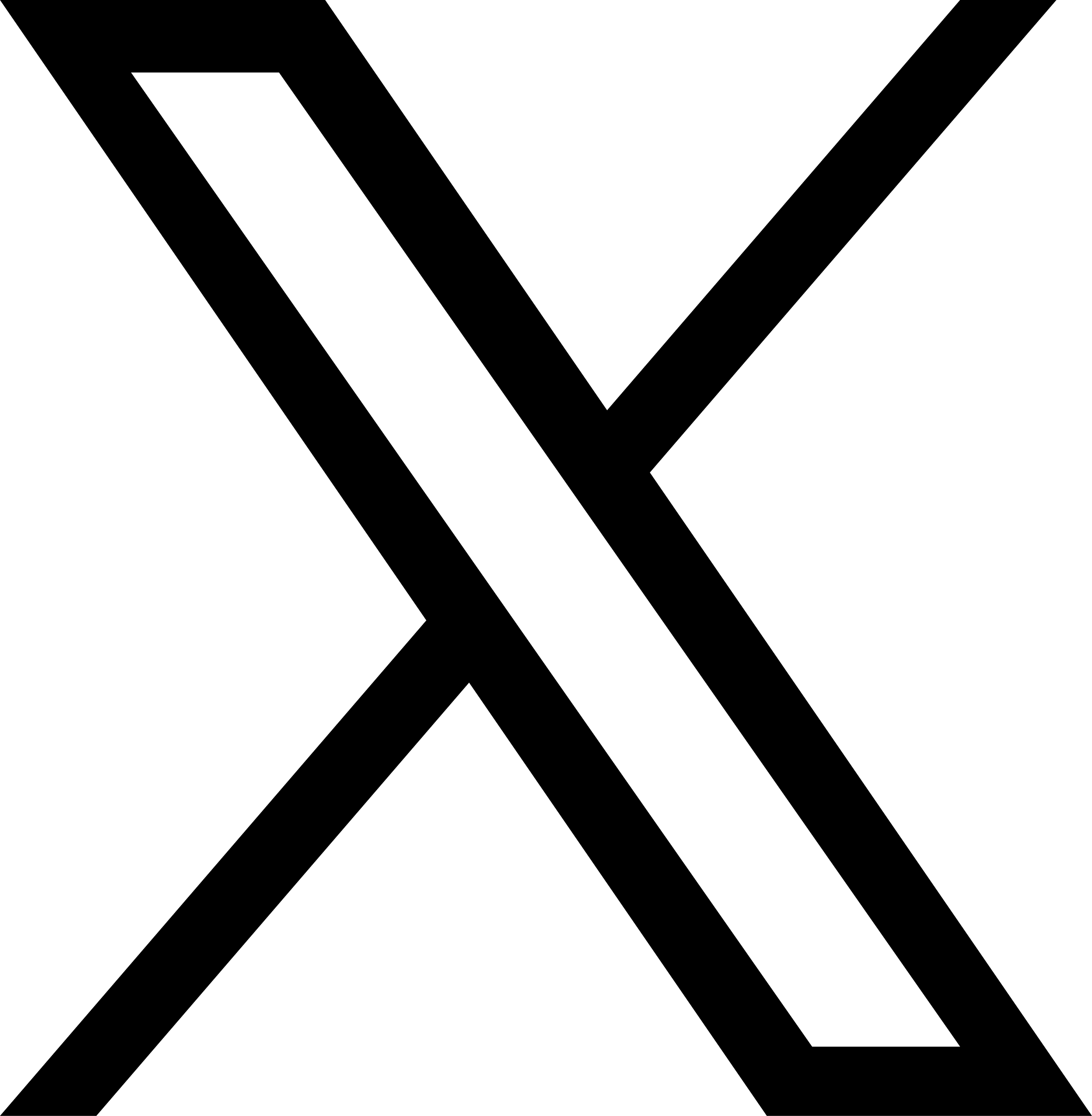厚生労働省が6月27日に公表した最新の「国民生活基礎調査」によると、貧困状態にある17歳以下の子どもの割合(子どもの貧困率)は、前回調査の2012年の16.3%から、最新の2015年は13.9%となり、2.4%ポイント(以下、「%pt」)改善した。
本稿では、子どもの貧困率低下の背景を統計的に探るとともに、いくつかの考察を加えたい。
子どもの貧困率が改善
貧困率をどのように計測するかは、さまざまな提案がなされているが、算出が簡便であり国際比較にも用いられる代表的な指標が「相対的貧困率」である。相対的貧困率は「貧困線を下回る可処分所得しか得られていない人の割合」で定義されているが、貧困線とは一人当たり可処分所得(等価可処分所得(注1))の中央値の半分で表される。2015年を例にとると、一人当たり可処分所得は244万円であるため、貧困線はその半分の122万円となり、可処分所得が122万円に満たない子どもが相対的貧困に該当する。3人家族を例にとると、世帯の可処分所得が211万円に満たない世帯の子どもが該当する。
子どもの貧困率(相対的貧困世帯に属する子どもの割合)の推移を示したものが図表 1である。子どもの貧困率は、景気変動などの影響を受けて若干の上下を伴いつつも、1980年代からほぼ一貫して上昇傾向にあり、2012年には16.3%に達していたが、2015年には13.9%まで大きく低下した。2012年には6人に1人が貧困状態にあったが、それが2015年には7人に1人にまで改善した。
図表 1 子どもの貧困率(相対的貧困率)の推移

(出所)厚生労働省「国民生活基礎調査」
(注)17歳以下を子どもと定義している。
子どもの貧困率はなぜ改善したのか
それでは子どもの貧困率はなぜ改善したのだろうか。公表データのみからでは厳密な分析は難しいが、いくつかの仮定を置きながら、子どもの貧困率の変化を、①大人が2人以上の世帯の貧困率の変化、②大人が1人の世帯(≒ひとり親世帯)の貧困率の変化、③ひとり親世帯の割合の変化、という3つの要因に分解したものが図表 2である。ここでは上述の「子どもの貧困率」ではなく、「子どもがいる現役世帯(世帯主が18~64歳世帯)のうち、一人当たり可処分所得が貧困線未満の世帯の割合」を子どもの貧困率の代理指標として用いている。
子どもがいる現役世帯の貧困率(一人当たり可処分所得が122万円未満の割合)は、2012年から2015年にかけて15.1%から12.9%へと2.2%pt低下しているが、もっとも大きな要因は大人が2人以上の世帯の貧困率が低下したことであり、1.6%pt分寄与している。次に大きな要因は、大人が1人の世帯割合が低下したことであり、0.4%pt分の寄与となっている(注2)。もっとも小さな要因は大人が1人の世帯の貧困率の低下であり、0.2%pt分の寄与となっている。
図表 2 子どもがいる現役世帯の貧困率の変化の要因分解

(出所)厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成
(注)本来は交絡項もあるが、非常に小さい寄与であるためグラフでは加味していない。
以上から分かるのは、子どもの貧困率が低下したのは、大人が1人の世帯(主としてひとり親世帯)の割合の低下が主因でなく、各世帯の貧困率が低下したことが主因だと言える。
次に、子どもの一人当たり可処分所得(等価可処分所得)の分布を2012年と2015年について描いたものが図表 3である。貧困線よりも所得の低い層の割合が低下し、貧困線より所得の高い200~360万円の層が増加していることが分かる。
図表 3 子どもの可処分所得の分布

(出所)厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成
図表 4は、子どもがいる世帯の平均所得金額について2012年から2015年にかけての変化を見たものである。総所得は、2012年の673.2万円から2015年は707.8万円へと35万円程度増えているが、その内訳をみると、雇用者所得が35万円ほど増える一方で、児童手当や社会保障給付は減少している。つまり、2012年から2015年にかけての貧困率の低下は、ほぼ賃金の増加によるものであり、社会保障等の充実によるものではない。
図表 4 子どもがいる世帯の平均所得金額の変化

(出所)厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成
それでは、賃金はどのように変化したのかを見てみよう。図表 5と図表 6は、一般労働者(フルタイム労働者)の1か月の所定内給与と、短時間労働者(パートタイム労働者)の時給の分布の変化をみたものである。両方のグラフから共通して分かることは、2012年から2015年にかけて低所得者の割合が減少し、中所得の割合が増加していることである。
図表 5 一般労働者の所定内給与(1か月)の分布の変化

(出所)厚生労働省「賃金構造基本調査」より作成
図表 6 短時間労働者の時給の変化

(出所)厚生労働省「賃金構造基本調査」より作成
まとめと考察
本稿では、子どもの貧困率の直近の動向を整理すると共に、貧困率低下の背景を統計データから探ってきたが、以下のようにまとめることが出来る。
第一に、子どもの貧困率は2012年の16.3%から2015年の13.9%にかけ2.4%ptと大きく低下した。ただし図表 7で示されているように、国際的にみると、日本の子どもの貧困率はOECD主要国のなかでまだまだ高い状況にある点は留意すべきである。
第二に、子どもの貧困率低下の要因は、低所得層の賃金の増加が主因であり、社会保障の充実等が理由ではない。
そのうえで、以下の点を指摘できる。
第一が、子どもの貧困率の今後のトレンドである。低所得層の賃金上昇の背景には、経済状況の安定的な推移と労働供給の減少に伴う人手不足があると考えられる。特に後者についてはそのトレンドが今後も継続する可能性が高いため、子どもの貧困率上昇のトレンドは一服するのではないかと考えられる。
第二が、政策支援の重要性である。今回の子どもの貧困率の改善は労働市場の構造変化に伴う賃金上昇が主因であり、社会保障等の充実によるものではない。政府は、2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させ、2014年には「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定するなど、対策を進めてきている。しかしながら、そうした対策の効果が数字に表れてきている訳ではなく、経済状況や雇用環境が悪化すれば、子どもの貧困率は再び急上昇する可能性が高い。今回の貧困率の改善をもって子どもの貧困対策の手綱を緩めてはならない。
第三が、貧困を多面的に把握していくことの必要性である。相対的貧困は、所得という単一の軸に基づく貧困の測定でしかない。現代の貧困は、経済的な貧困だけではなく、関係性の貧困、機会の格差、健康格差、リテラシーの格差など、多面的な形で表れており、必要な支援も多様化している。ノーベル経済学者のアマルティア・センは、必要に応じて人々が選択できる「機能」の集合を「ケイパビリティ(capability、潜在能力)」と定義し、ケイパビリティを高めていくことの重要性を説いた。今後は、子どもの貧困の実態を多面的にとらえながら、適切な支援に結び付けていくことが求められる。
図表 7 子どもの貧困率の国際比較

(出所)OECD Statisticsより作成
(注)2012年以降の最新年の数値であり、各国ごとに時点は異なる。
(注1)等価可処分とは、世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で除したものである。。なお、可処分所得を世帯人数の平方根で除する意味などについては、厚生労働省「国民生活基礎調査(貧困率)よくあるご質問」http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21a-01.pdfなどを参照されたい。
(注2)国民生活基礎調査によると、子どもがいる現役世帯の2015年の貧困率は、大人が1人の場合は50.8%、大人が2人以上の場合は10.7%となっている。そのため、大人が1人の世帯の割合が減少すると、それぞれの貧困率に変化がなかったとしても、日本全体の貧困率は低下することになる。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。