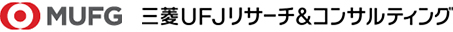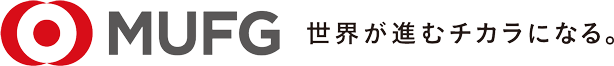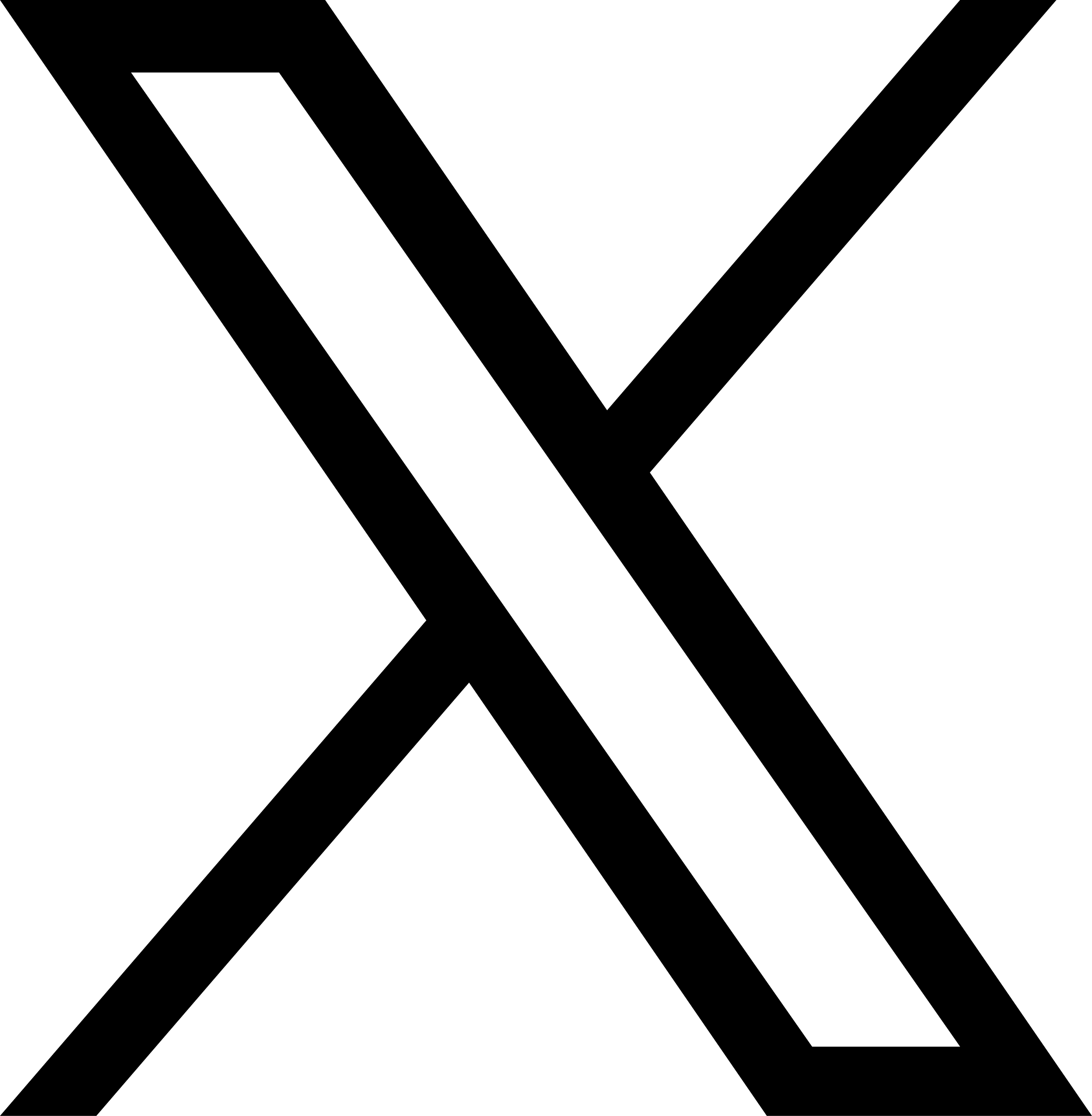高齢期の所得保障を考えるシリーズⅡ:公的年金の給付水準引き上げに向けて公的年金の給付水準引き上げに向けて
6月に公表された金融庁報告書を契機に、再び公的年金制度への不信感を強調するような言説が広まっている。しかしながら、我が国の公的年金制度は、「拠出建て」と「マクロ経済スライド」という設計により、年金給付を賄う財源がなくなり破綻する、ということが(設計通り運用される限り)原理的に起こり得ない仕組みとなっている。
この仕組みは、2004年の年金改革により導入された。従来の公的年金制度は、まず給付水準を決めた上で、必要な保険料を徴収するという「給付建て」の仕組みであったが、この下では、少子高齢化の進展により現役世代に過重な保険料負担が生じる懸念があった。そこで、まず負担の上限(厚生年金保険料率18.3%、国民年金保険料16,900円(2004年度価格)/月1)を決めた上で、収入の範囲内に給付を抑制する拠出建ての仕組みへと切り替えられた(図表 1)。そして、この給付を抑制する自動安定化装置として、マクロ経済スライドがビルトインされた。
図表 1 給付建てと拠出建ての違い(イメージ)

本来、年金額は賃金(物価)上昇率に応じて毎年度改定されるが、マクロ経済スライドが発動すると、本来の改定率から「スライド調整率」(=「公的年金全体の被保険者の減少率の実績」+「平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)」)が差し引かれる。つまり、公的年金の支え手の減少と、受け手の増加に応じて、年金額が抑制されていくのである。
マクロ経済スライドによる調整は、基礎年金については国民年金財政が、厚生年金については厚生年金財政が、それぞれ安定するまで続けられる。ここで年金財政の安定とは、100年後に給付費の1年分の積立金が残ることを指す。調整が終了した後は、本来通りの改定ルールに戻るため、所得代替率2は原則として一定となる。
なお、いくら破綻しないと言っても、少子高齢化が進む我が国では、際限なく給付水準が切り下げられる、という懸念も生じ得るが、長期的には公的年金の支え手と受け手の人口バランスが安定するため(図表 2)、マクロ経済スライドによる調整もいずれ終了する(後述する通り、問題は早く終了するか、遅く終了するかである)。
図表 2 我が国の人口バランスの推移(1950年~2100年)

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」等より作成
ただし、給付水準の低下自体は避けられず、この「痛み」をいかに緩和し、年金の所得保障機能を確保していくかが重要となる。その具体策として、2014年の財政検証では「オプション試算」という形で、3つの改革メニューの効果が試算されている。
オプションⅠは、「マクロ経済スライドの見直し」である。本稿冒頭で、「設計通り運用される限り」と述べたのは、実際にはマクロ経済スライドが持つ機能を発揮できない状況が続いてきたためである。マクロ経済スライドには、「名目下限措置」と呼ばれるルールが存在し、本来の改定率(賃金(物価)上昇率)が小さく、マクロ経済スライドによる調整で名目の年金額が前年度よりも減額となる場合は、年金額が据え置かれることとなっている。また、本来の改定率がマイナスの場合(賃金(物価)が下落している場合)は、そもそもマクロ経済スライドが発動されない。つまり、マクロ経済スライドがその機能を果たすには、賃金(物価)が安定的に上昇し続けることが前提条件となる。
このため、賃金(物価)が低迷した過去15年間で、マクロ経済スライドが発動したのは僅かに2度(2015年度、2019年度)であり、結果として所得代替率は低下するどころか上昇した。図表 3で示す通り、マクロ経済スライドは早期に発動されるほど、調整が短期間で終了し、所得代替率の低下が小幅に止まる仕組みとなっている。現在の受給者にとっては「痛み」の伴う調整であるが、これにより子や孫の将来の給付水準を底上げすることができるのであり、公平性の観点から、名目加減措置のルールは速やかに廃止されることが望ましい3 。
図表 3 マクロ経済スライドの発動時期による所得代替率の違い(イメージ)

オプションⅡは、「被用者保険の更なる適用拡大」である。厚生年金の適用対象となるのは、所定労働時間が週30時間以上4の者であり、これに達しない短時間労働者が厚生年金ではなく国民年金へ加入した結果、国民年金に加入する第1号被保険者の4割を被用者が占めるに至っている。マクロ経済スライドによる給付抑制の影響は、国民年金財政の安定化に時間が掛かることから、厚生年金よりも基礎年金で大きくなるため、なるべく多くの被用者を厚生年金の網に掛けることが肝要である5。
オプションⅢは、「保険料拠出期間と受給開始年齢の選択制」である。引退年齢が上昇していく中で、可能な限り長く保険料を納め、それによって給付水準が高まるよう、保険料拠出期間を延長することが望ましい。また、高齢期のライフスタイルやワークスタイル、家計や健康の状況は千差万別であるから、受給開始年齢(及びそれに応じた給付水準)の選択範囲を拡大することで、高齢期の所得水準を底上げする選択肢を提供することも重要である。
以上3つのオプションについて、所得代替率の引き上げ効果を図表 4に示す。試算結果を見ると、いずれのオプションも、特に基礎年金の給付水準を大きく引き上げる効果を持つことが分かる。また、制度改革に加えて、受給者が繰下げ受給を選択することで、受給額をさらに大きく底上げすることが可能となる(オプションⅢ(拠出期間延長+繰下げ))。
図表 4 オプション試算の結果(2014年財政検証)

(出所)第21回社会保障審議会年金部会資料(2014年6月3日)より作成
(注1)財政検証では、C・E・G・Hの4ケースについて、オプション試算が行われているが、本稿では、そのうち中央の2ケースの結果を紹介している。
(注2)オプションⅠは、物価・賃金の伸びが低い場合でもマクロ経済スライドがフルに発動するシナリオ、オプションⅡ②は月額賃金5.8万円以上の全被用者(約1,200万人)へ適用拡大したシナリオ、オプションⅢ(拠出期間延長)は基礎年金給付算定時の納付年数上限を40年から45年へ延長し(これに合わせて基礎年金も増額)、65歳以上の在職老齢年金も廃止したシナリオ、オプションⅢ(拠出期間延長+繰下げ)はこの制度変更を前提として67歳まで就労し(厚生年金適用)、受給開始を繰下げたシナリオである。
(注3)オプションⅠの試算では、景気変動を加えているため、現行の仕組みを維持した場合の最終所得代替率はオプションⅡ・Ⅲの試算と僅かに異なる。
(注4)「比例」は厚生年金の報酬比例部分、「基礎」は基礎年金を指す。
これらのオプションは単体で実施しても効果はあるが、組み合わせて実施すれば、一層大きな効果が望めるだろう。重要なことは、こうした客観的なファクトを押さえた上で、できるだけ早期に改革に着手することである。金融庁報告書の一件を奇貨として、前向きな議論が展開されることを期待したい。
1 なお、給付抑制を避ける(2004年当時の給付水準を維持する)ためには、厚生年金保険料率22.8%、国民年金保険料20,700円(2004年度価格)/月(いずれも基礎年金の国庫負担を1/2とした場合)まで、負担を引き上げる必要があった。
2 所得代替率とは、現役世代の賃金を100%としたときの、相対的な年金給付水準を表す指標である。所得代替率の定義は各国で異なるが、我が国では、被用者の夫が平均賃金で40年間働き、妻は40年間専業主婦であった「モデル世帯」の年金額を、現役男性の平均可処分所得で除して求める。
所得代替率=(夫の厚生年金+夫婦の基礎年金)÷現役男性の平均可処分所得
3 なお、マクロ経済スライドではなく、支給開始年齢の引き上げによって、給付水準を確保すべきとの意見もある。しかしながら、支給開始年齢の引き上げの「痛み」は、現在の受給者には及ばず、将来の受給者のみに及ぶため、公平性の観点からは劣後すると言える。
4 従業員規模501人以上の企業の場合は、所定労働時間が週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤務期間1年以上見込み、学生でないこと、が条件である。
5 なお、被用者保険の適用拡大の便益は、厚生年金に加入できるようになる短時間労働者にのみ及ぶものではない。多数の被用者が厚生年金へ移り、国民年金の支出が減少することで、国民年金の積立度合(=積立金÷支出)が改善し、マクロ経済スライドによる調整が早期に終了するため、基礎年金の給付水準が上昇する。これは、全ての年金受給者に便益が及ぶ改革であり、積極的な適用拡大が望まれる。ただし、基礎年金の給付水準上昇は、財源の1/2を賄う国庫負担の増加にもつながるため、この財源の確保が必要である点には留意しなければならない。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。