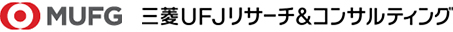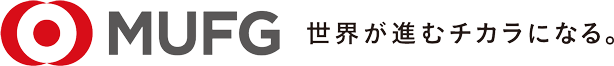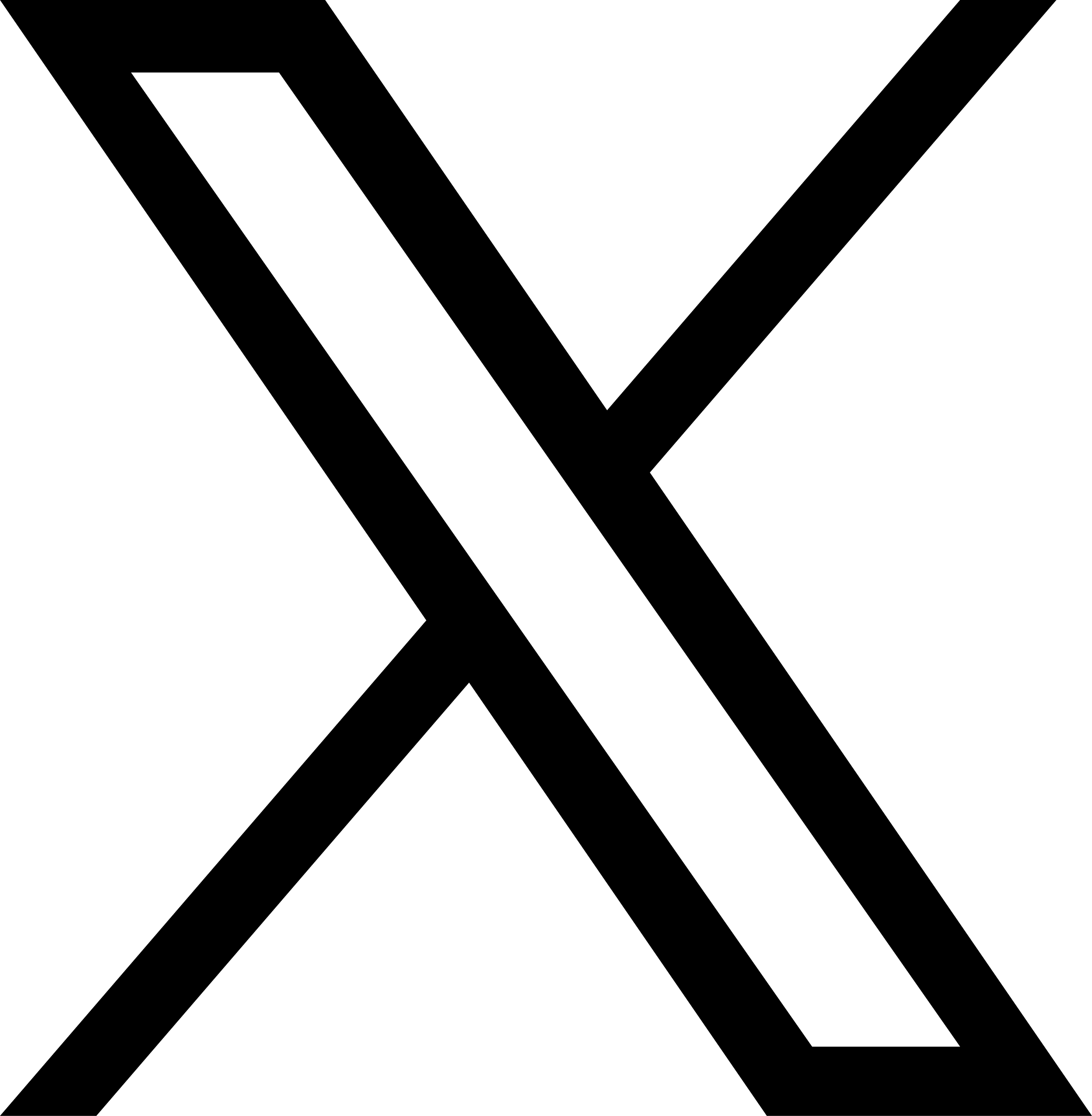○ベトナム経済は、中国経済と並んで、アジアでも群を抜く高成長と安定性を示してきた。これを可能にした政策面の要因として、外資導入による工業化を軸とした成長路線と、短期資本移動・為替取引の規制によって海外金融市場から国内経済への直接的な影響を遮断したという2点が重要であった。
○近年のベトナムの経済成長率は、WTO加盟(2007年)直後のブーム期よりも低下している。これは、ベトナム政府が2010年以降、不動産バブルとインフレを退治するため引締めに転じたことが影響している。引締めにより、景気は鈍化したが、2011年に一時20%を超えていたインフレ率は足元で5%を下回った。
○ベトナムの輸出は、相変わらず好調である。近年、輸出の主役は、従来の一次産品・軽工業品から携帯電話や半導体などのエレクトロニクスへと変わりつつある。輸出の急拡大により、慢性的な赤字だった貿易収支が2012年に黒字に転じ、その影響で恒常的な赤字に陥っていた経常収支も黒字化した。
○経常収支が黒字に転じた影響で、一方的な下落を続けてきたベトナムドンの為替相場は下げ止まってほぼ横這いとなり、そうした為替相場安定が物価の安定にも寄与する形となった。また、経常黒字を背景に外貨準備も2011年初の100億ドルから2014年初には300億ドルまで積み上がった。ただし、外貨準備は輸入の3カ月分に過ぎず、依然として安全な水準とは言えない。
○海外からの直接投資は、一件当たりの投資額が小規模化しており、中小企業の進出が増えていることがうかがえる。これは、裾野産業が拡充しつつあることを示すものとも考えられる。日本企業は、生産拠点としてのベトナムの最大の強みは、労働力の質の高さと低賃金にあると考えている。
○ベトナム経済は、近年、成長率が低下したものの、それによって、対外不均衡拡大や物価上昇に歯止めがかかり、マクロ経済が、よりサステイナブルな方向へ移行しているとも言える。今後、中長期的に成長を持続するため、ベトナムの経済運営は、需要を刺激する成長一辺倒の戦略ではなく、不均衡・非効率を解消するような供給サイドの構造改革へと重点を移していくべきである。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。