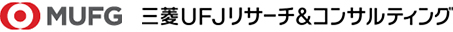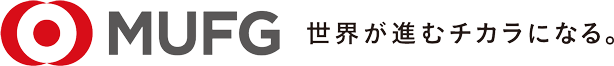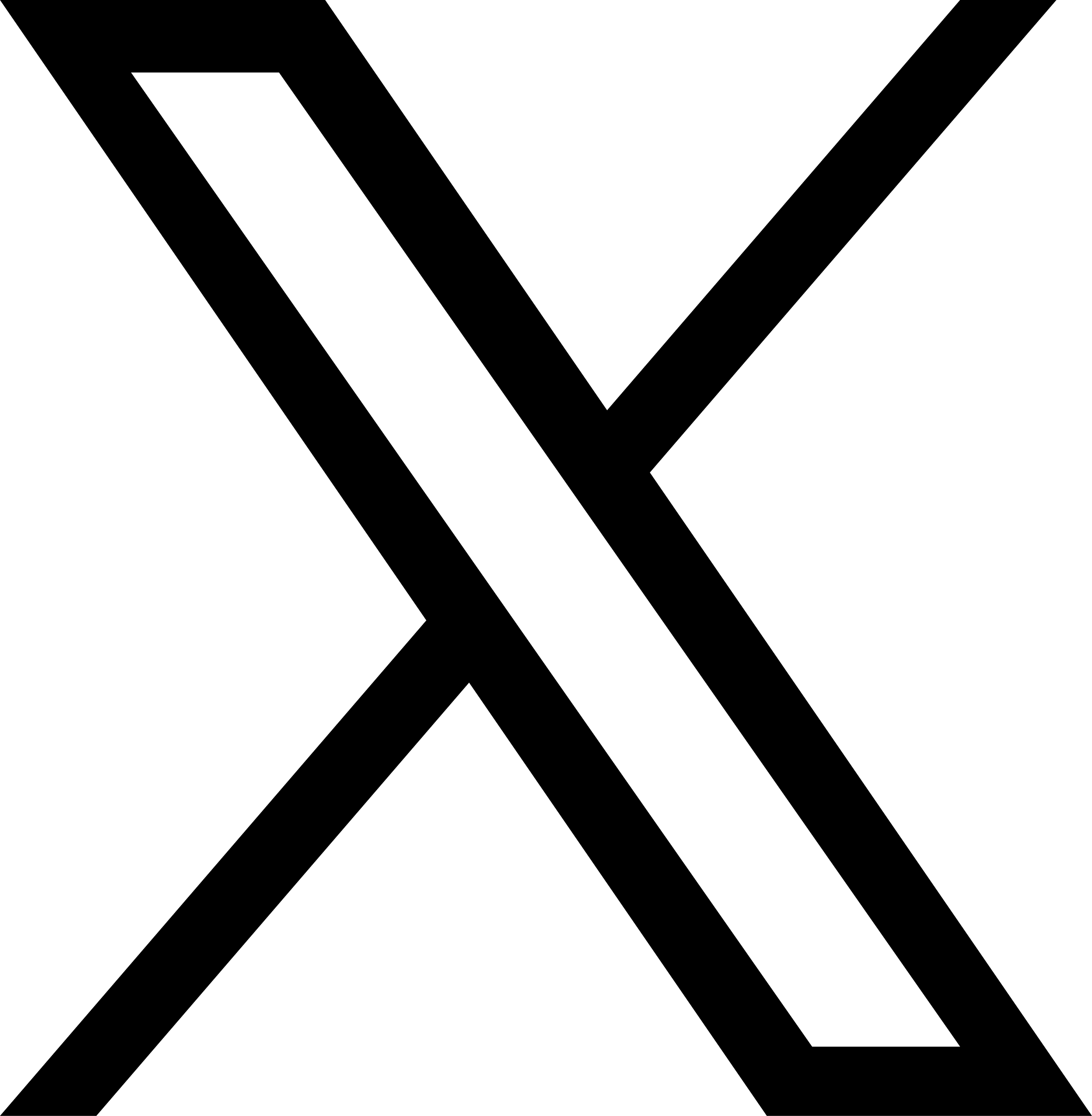- 中南米地域では、最近の相次ぐ左派政権成立によって、経済の先行きに不透明感が漂いつつある。今年に入ってから、チリ、ペルー、コロンビアで左派政権が発足し、10月のブラジル大統領選挙でも左派の労働者党候補が勝利し、これによって、中南米主要7カ国が全て左派政権となった。中南米諸国の経済は、財政赤字など構造的な課題を抱えているが、バラマキ型の経済政策を指向しがちな左派政権が成立したことで、経済構造改善への道は険しくなった。
- 中南米経済の大きな弱点は財政赤字体質である。ブラジルやアルゼンチンでは、政府が低所得層向けの給付金支給拡大や公務員の賃金大幅引き上げなどのバラマキを実施したため、財政赤字が深刻化した。そこで補助金を減らした結果、公共料金が上昇しインフレが昂進、それを抑制するための利上げで景気後退に陥った。財政規律低下を起点としてインフレが昂進し、それが引き金となって経済失速というのが、中南米経済にありがちなパターンと言えるだろう。
- 中南米経済の特徴として、経常収支がほぼ慢性的に赤字であることがあげられよう。中南米の多くの国々では、輸出品目の主力が原油や金属資源などの一次産品であり、輸出品の付加価値が低いため、貿易黒字を安定的に維持することが難しい。この経常赤字は、前述の財政赤字と相俟って、中南米諸国の通貨安・インフレを引き起こす主因となってきた。
- 中南米経済を悩ませてきた問題が「インフレ体質」である。特に、南米大陸地域では、かつて、激しいインフレに見舞われており、1980年以降だけを見ても、ペルー、アルゼンチン、ブラジルなどで、外貨不足や財政規律喪失に起因する数千パーセントの猛烈なハイパーインフレーションが発生している。2000年代以降、中南米のインフレ率は以前より大幅に低下し比較的安定していたが、2017年以降は再加速している。
- 中南米地域の経済成長率はASEAN-5より低く、その理由のひとつに投資の低迷があげられる。中南米はASEAN-5よりも投資率(投資/GDP)がかなり低い。中南米の投資率が低いのは、そもそも貯蓄率(貯蓄/GDP)の低さが影響していると考えられる。かつて激しいインフレーションに襲われたトラウマが残る中南米では、安心して貯蓄を積み上げることができるほど財政・金融に信頼感がない。今後、貯蓄率・投資率を高めるには、財政・金融規律を維持することが重要である。
- 中南米で左派政権が優勢な理由のひとつが、所得分配の不平等の大きさである。多くの中南米諸国では、社会階層が少数の富裕層と多数の低所得層に分断され、多数派の低所得層がバラマキや所得再分配を重視する左派政権を支持するため、選挙で左派政党が勝ちやすいという構図が生まれる。また、左派政権は、経済運営の失敗で退陣しても、中道右派政権による痛みを伴う構造改革に耐えられなくなった大衆の支持ですぐに政権に返り咲いてしまうというパターンになりがちである。
- ただ、左派政権になったと言っても、中南米主要国の経済状況が一律に悪化するとは限らない。チリやペルーなどのように新自由主義的な経済政策を実施し経済不振に陥らない可能性が高い国もある。その意味で、今後、各国の具体的な経済運営方針がどうなっていくかが注目される。
テーマ・タグから見つける
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。
テーマ
テーマ