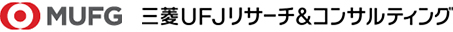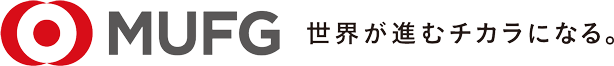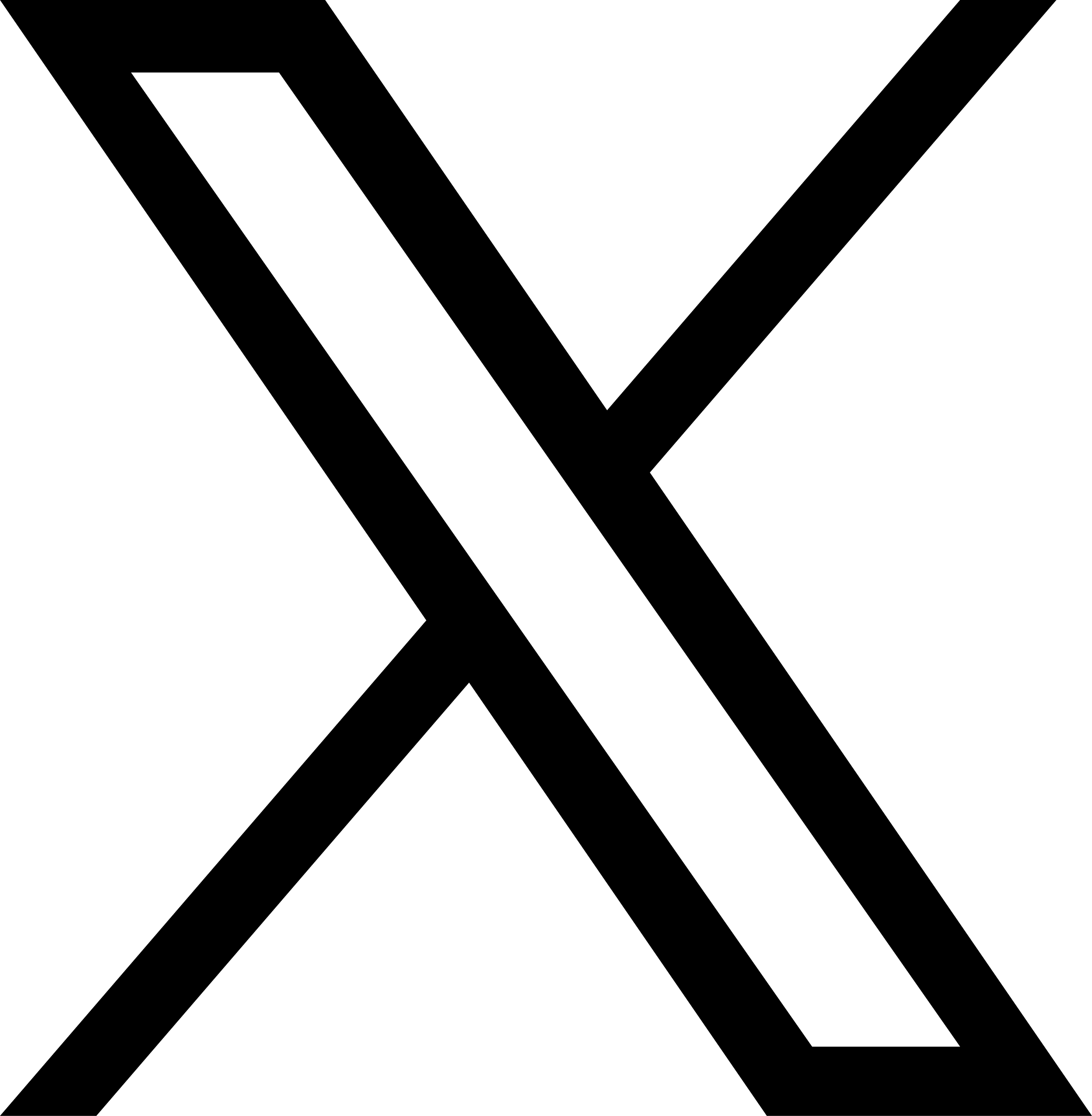世界経済のリスクファクターとして、新興国通貨下落の可能性が注目されている。2010年以降の新興国通貨の対米ドル為替相場の長期的な動きを振り返ってみよう。2013年頃から、米国の金融緩和終焉観測を受けて、新興国通貨は全般的に下落傾向となり、さらに、一部の新興国では、経済運営の歪みや対外関係悪化などが引き金となって、通貨が大幅に下落した。アルゼンチンでは、ペロン党左翼政権による放漫財政や保護主義などへの不安感から通貨ペソが売られ、対米ドル為替相場は2010年1月からの10年間で20分の1にまで下落した。また、トルコでは、経常赤字やインフレが拡大する中でも金融緩和を強行するというエルドアン政権のヘテロドクスな金融政策への不信感や、対米・対EU関係の悪化などへの不安感から通貨リラが売られ、対米ドル為替相場は2010年1月からの10年間で5分の1に下落した。さらに、ブラジルでは、左翼の労働者党政権によるバラマキ型の経済運営への不安感や政治家による汚職への不信感から2013年以降通貨レアルが売られ、為替相場が急落した。その後、レアル相場は、2016年の労働者党政権退陣を契機に持ち直した。このほか、ロシアでも、ウクライナ紛争に絡む米・EUによる対ロシア経済制裁発動と、主力輸出品の原油の価格下落というダブルパンチに見舞われて、通貨ルーブルが売られ、為替相場が2014年に急落した。こうした為替相場の急落は、輸入物価高騰を通じてインフレ率を急上昇させ国民生活の窮乏化を招き、また利上げ圧力を高め景気刺激のための金融緩和政策を中断させるという形で、新興国経済に大きな痛みをもたらした。
他方、新興国通貨の先行きへの不安を高める大きな要因となっているのが、米国金利の今後の動きである。新興国の経済成長には、「米国の低金利」が不可欠な要件である。それは、過去の新興国経済の成長と米国金利水準の関連性を見れば明らかである。新興国経済の2000年代の高成長の背景には、米国の金利が歴史的な低水準だったことが大きく影響している。米国では、同時多発テロ事件直後の景況感悪化に対応するため、2001年に政策金利であるFF(Federal Fund)金利が大幅に引き下げられ40年ぶりの低水準となった。その結果、ハイリターンを求めて資金が米国から新興国にシフトし、新興国経済への強力な追い風となった。その後、米国のFF金利は、インフレ懸念の高まりに対応する形で2005年頃から上昇したが、リーマンショック発生直後に大幅に引き下げられ、しばらく金融緩和局面が続いた。しかし、米経済回復を受け、2013年には金融緩和終焉観測が浮上し、その際、上述のように新興国から資金逃避が発生、新興国通貨が下落し、新興国経済に大きな混乱を生んだ。今般のコロナショック発生直後に、FF金利は引き下げられたが、今後の米国景気回復に伴って、2022年にはFF金利の引き上げが開始される見込みであり、米国の金融緩和モード終了が、新興国の各国通貨を下落させ、それに対応するための各国の利上げが景気の腰折れをもたらすのではないかという警戒感が高まっている。
新興国通貨の対米ドル為替相場のこれまでの全体的な傾向としては、アジアの通貨は比較的堅調であるが、非アジアの通貨が軟調である。特に、ロシアは、ウクライナ侵攻に対する米欧日による懲罰的な金融・経済制裁の影響を受け、大幅な通貨安に見舞われており、経済が低迷状態に陥る可能性が高い。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。