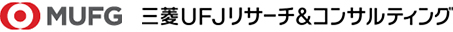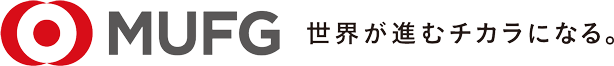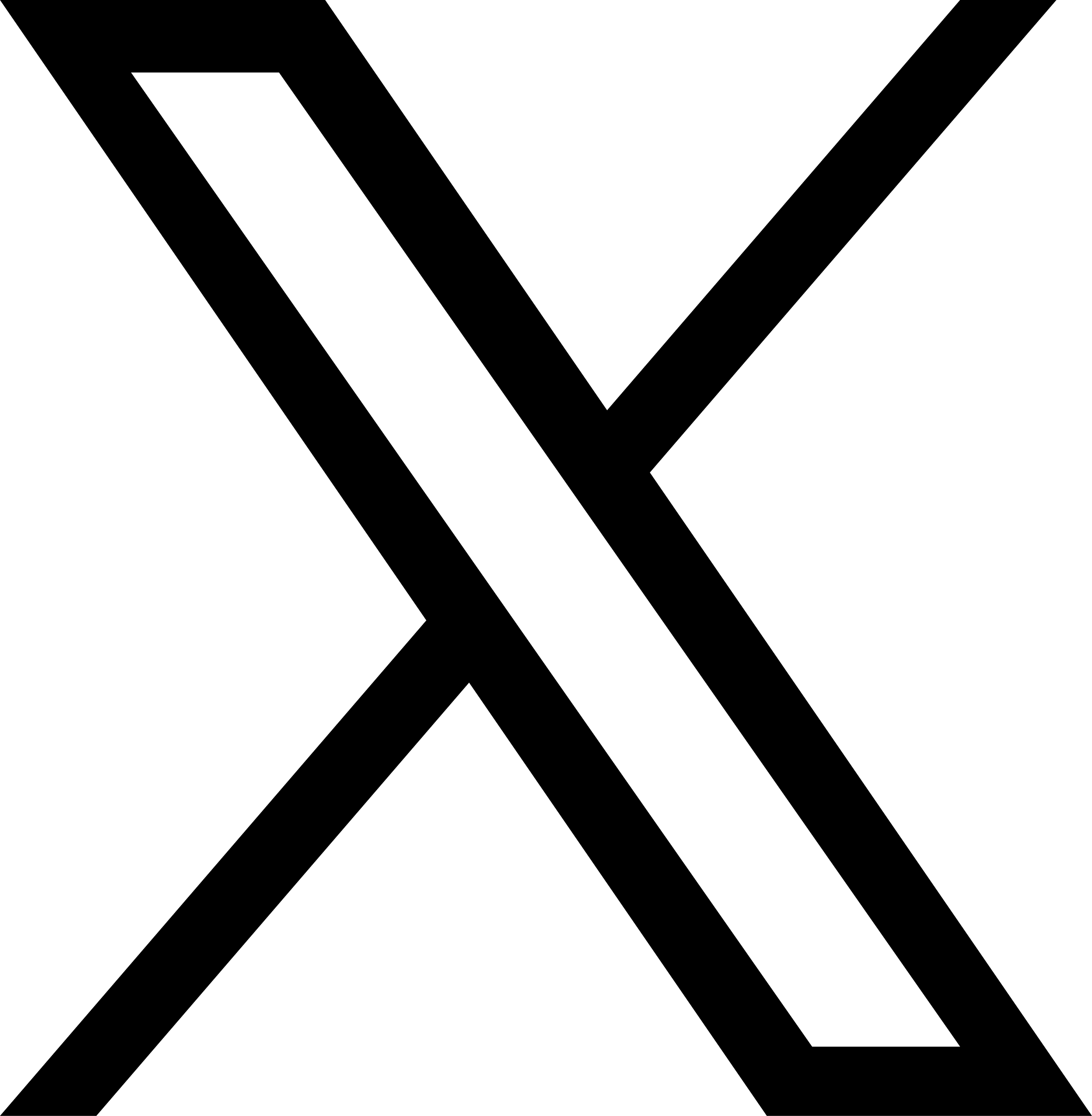気候変動への“適応”に向けて企業のとるべき戦略~サステナビリティ戦略✕市場機会および気象ビジネスの可能性~
当社はシンクタンクとして、未来洞察や未来社会構想というアプローチから、社会課題解決に向けた方法論・仕組みの検討に取り組んでいる。昨今、極めて重要な社会課題として認識されている「気候変動」に対し、“緩和”(脱炭素)でなく“適応”による対策の具体化に向けても、気候変動が進んだ状態での社会・産業や、ライフスタイルについての予測が重要になる。したがって、未来洞察および未来社会構想が極めて重要なアプローチとなると言えるだろう。本レポートでは、「気候変動への適応」に対し、サステナビリティ・TCFDの考え方や動向を踏まえて、民間企業における戦略策定について取り上げる。特に、未来洞察という新たなアプローチから、気候変動への“適応”の重要性と、企業が戦略・打ち手として“適応”に取り組む意義について論じる。
1.気候変動に対する“緩和”と“適応”に関する国内外の動向
昨今、気候変動の問題は世界各国の最重要アジェンダのひとつになっている。2015年12月に国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定において、世界の平均気温上昇を産業革命前とくらべて1.5℃に抑える努力目標が設定された。そして、2021年8月、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、第6次評価報告書(AR6)を発表し、「温暖化の主因は人間活動」と初めて断定するとともに、「今後数十年間にCO2を大幅に削減できなければ、2100年までに気温上昇が2℃を超える」と指摘した。1.5℃に抑えるためには相当に高いCO2排出量削減目標を掲げる必要がある一方で、2022年11月にエジプトで開催されたCOP27で採択された「シャルム・エル・シェイク実施計画」の中では、1.5℃目標に向けた具体的な指針を示すには至らなかった。
国内でも、2020年10月、菅内閣総理大臣(当時)により「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」というカーボンニュートラル宣言が発出された。これにより、全産業、各企業に高い脱炭素目標が求められることとなった。帝国データバンクのアンケート調査[ⅰ]によると、温室効果ガスの排出抑制に取り組む企業は8割を超える一方、6割を超える企業が目標達成は困難と回答している。
環境省の定義によると、上記のように脱炭素(温室効果ガスの排出削減と吸収)により、世界の平均気温の上昇を抑制する方策は、気候変動の“緩和”策と呼ばれている[ⅱ]。一方で、既に生じている、あるいは将来予測される気候変動の影響に対して手を打つ方策は、気候変動への“適応”策と呼ばれている。
地球上で気候変動による影響・被害が顕在化しつつある潮流を踏まえ、日本でも気候変動への適応策に取り組むべく、2018年6月に「気候変動適応法」が成立した。そして、2018年12月、気候変動影響および適応に関する情報の集約と発信・取り組み支援を担う「気候変動適応センター」が国立環境研究所に設立された。
2.気候変動がもたらす影響の特徴
本章では、気候変動への“適応”に向けて企業が取るべき戦略について、気候変動が社会や産業・ビジネスにもたらす影響の特徴を踏まえ、過去に当社が発表したレポートから、気候変動への“適応”に求められる視点を提示する。
企業として気候変動への“適応”に向けた戦略・打ち手を考えるためには、気候変動が、社会や産業・ビジネスにどのような影響を与える可能性があるか、広い範囲で捉える必要がある。
気候変動により起こり得る事象のうち、わかりやすいものとして知られているのは海面上昇や風水害、暑熱などである。これらの影響は、既に建築・インフラ系の業界、または保険業界では、ビジネスに織り込んで検討している。たとえば建築・インフラ業界では、国土強靭化・レジリエントの一環として災害対策に取り組む中で、気象条件による構造物シミュレーション、災害に強い構造物設計や素材開発の研究をしている。これらは、気候変動の“適応”につながる取り組みといえる。さらに、保険業界では、火災保険や天候デリバティブに代表されるように、天候リスクをカバーする金融商品が既に存在しており、気候変動による影響に対しても、天候や災害によるものであれば、保険サービスが大きく貢献することが見込まれる。
しかしながら、海面上昇や風水害、暑熱は、気候変動による影響のほんの一部にすぎない。気候の地域特性の変化や、対流性気象擾乱の活発化、生態系の乱れ、パンデミックを含めた健康被害など、幅広く影響を与えうる可能性が指摘されている。現状は、気候変動によってどのような影響がおよぼされるか、その全貌が十分に解明されておらず、社会や産業・ビジネスへもたらす影響を推定するのは、難易度が高い。気候変動のようにその影響の全貌の理解が難しい社会課題に対しては、科学的な分析結果をベースに、ある程度仮定や前提を置いた形で、未来社会・産業に対する影響の洞察が求められる。当社では過去に、地球温暖化による南北の熱交換、海面からの水蒸気補給の活性化による“対流性気象擾乱”(短時間強雨、突風、落雷、ひょう)による影響にフォーカスし、社会や産業・ビジネスの未来像を洞察するレポートを発表した。(「ポスト温暖化の未来予測」[ⅲ])
同レポートでは、厳しい環境に適応するための都市・インフラや、新たな産業・ビジネスモデルに関する未来像を洞察した。気候変動への“適応”が、新たなライフスタイルの創造や、新たな市場機会に繋がる可能性があり、これまでにないビジネスモデル・事業プロセスを検討するチャンスになると結論付けた【図表1】。

3.企業のサステナビリティ戦略の視点から検討する気候変動への“適応”策
本章では、企業のサステナビリティ戦略の視点から、気候変動への“適応”に向けた打ち手を検討する。
サステナビリティ戦略においては、さまざまな社会課題に対して、「自社にとってのリスク」「自社にとっての機会」の両側面から戦略や打ち手を考える必要がある。
前述のような建築・インフラ系業界、保険業界で対応されている内容は、リスク対応の視点であり、サステナビリティ戦略の中に位置づけることができる。つまり、経営戦略の中でも、防災、レジリエンス、ERM(全社リスクマネジメント)、BCP(事業継続計画)といった分野において、気候変動によるリスク対応の検討が一部進んでいるといえる。
一方、前述した当社の分析では、気候変動への“適応”は、市場・事業としての機会として捉えられる可能性も指摘した。昨今、気候変動に対する企業の指針としてTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への対応が推奨されている。(詳細はTCFDコンソーシアムHP参照[ⅳ]) TCFDにより各社が開示を求められる内容は、ほとんどは気候変動の“緩和”に向けた脱炭素の視点となっている。一方で、気候変動により起こりうる気候パターンの変化や、海面上昇、洪水、干ばつ、異常気象などを指す「物理的リスク」への対応は、“適応”の視点に基づいた内容になっている。したがって、気候変動適応に向けた方針を考える上で、「物理的リスク」に則した“リスク対応”の視点、“市場・事業としての機会”の視点双方が重要になる。
改めて、気候変動への“適応”に対する打ち手を俯瞰すると、“リスク対応”の視点は既に進みつつある一方、“市場・事業としての機会”の視点はまだこれからといった状況だ。“リスク対応”は、将来の潜在的な損害のために多額の投資が必要になることから、社会・経済としてその原資を確保する必要があることが大きな課題となっている。その際に“市場・事業としての機会”も捉え、経済的価値創出により得られた利益をリスク対応に投資することがひとつの解決策になる可能性がある。したがって、難易度は高いものの、気候変動による社会や経済・ビジネスへの影響を洞察し、新たな市場・事業としての機会を検討することが極めて重要である。
レポート「ポスト温暖化の未来予測」で言及した通り、「ポスト温暖化」によって、これまで経済活動、日常生活で当たり前だった気象条件の前提が、根底から覆る可能性がある。そうなると、世の中の仕組みについてもマイナーチェンジではなく、本格的にスクラップアンドビルドの考え方が重要になる。よって、産業構造やビジネスモデル、都市・インフラ、ライフスタイルなどが一新される可能性があり、新たなニーズと市場、それに関する新たなビジネスモデル、事業プロセスを検討するチャンスと捉えることができる。

4.気象ビジネスへの期待
本章では、気候変動への“適応”を契機に、今後大きく発展する可能性があるビジネスモデルとして、気象ビジネスを取り上げて概説する。
気象ビジネスとは、気象情報そのものの提供や、気象情報を活用したコンサルティングなどのサービスが含まれる、いわゆる気象予報と予測データ利活用による価値提供を総称した概念である。最もポピュラーなサービスとして、お天気キャスターによる天気予報や、スマホに配信される気象情報提供などがある。
また、このようなエコシステムを支えている、いわゆる百葉箱から人工衛星に至る気象観測機器、分析・予測に活用するスーパーコンピューターのような気象予報・活用インフラや、雨具や防寒具といった消費者向けの身の回り品も、広義の気象ビジネスに含んで考えることができる【図表3】。

今回の分析において、気候変動による当該ビジネスへの影響を考えるために、「気象予報自体の価値」に着目する。
我々は日々気象情報を確認しながら、服装を決め、傘を持参するかどうか判断したり、雨雲が来ないであろう時間帯を選んで移動したりしている。それだけ気象予報は日常に入り込んだものである一方、仮に天気予報を見なくても、多少雨に濡れたり、寒さを我慢したりする程度なら、生活にそこまで支障をきたすことはない。もちろん日照時間、降水有無、風の様子、温度の多少の変化に影響を受ける農業や再エネ、小売などの一部の産業では気象予報は重要なファクターとなるが、屋内での活動がメインとなる多くの業態ではクリティカルなファクターにはならないだろう。
しかしながら、これらの認識は、気象条件が概ね安定的で予測可能であるという前提に立っており、気候変動は、前提となる気象条件を乱す可能性がある。これまでイレギュラーだった気候・気象が日常化し、毎日ゲリラ豪雨に見舞われる、日照のない日が長く続く、季節外れの異常昇温が増える、といった状況が当たり前になる可能性がある(「ポスト温暖化の未来予測」[ⅲ])。そのため、気象条件の変化に敏感になりながら経済活動や日常生活を送っていく必要が出てくるだろう。
そうなると、気象情報を日々着実に確認し、業務での損失や健康被害などに備える必要が出てくるため、気象予報の価値が格段に高くなると考えられる。したがって、気候変動が進むにつれて、気象予報、予測情報活用などの気象ビジネスが今後重要になることが見込まれる。
以降、気候変動適応の文脈で有望となりうる分野を3つ挙げる【図表4】。
(A)物理的リスクをベースとした気候変動“適応”コンサルティング
予報データを活用したBtoB(法人向け)、BtoG(政府・自治体向け)ソリューションサービスは気象情報を活用したサービスの代表格だが、ニーズはあるものの、一部の用途を除いては、費用対効果の点でビジネス成立の難易度が高かった。しかし、気候変動によってイレギュラーな気候・気象が日常化することで、これまで当たり前だったビジネスモデルや業務プロセスの見直しが求められる。そこで気候変動による物理的リスクを定量化し、社会・産業変化を洞察することは、気候変動への“適応”を意図したビジネスモデル刷新や、BPR/DXなどの支援に繋がると考えられる。
(B)高密度気象情報取得・分析インフラ
イレギュラーな気候・気象が日常化することで重要になるのが、予報メッシュ・更新頻度の精細化である。そのための観測網や、高性能演算装置に、人工衛星データやUAM(Urban Air Mobility:ドローン・空飛ぶ車などの空モビリティ)による点群データ、量子コンピューティングを含むスーパーコンピューターが活用できる期待が大きい。これらのインフラは単独では極めて高価だが、多用途に活用することで費用対効果が見合う可能性があるため、大型投資を通じた気象ビジネス参入が期待される。
(C)“適応”文脈による新製品・ソリューション開発+既存ビジネスリブランディング
(A)(B)は気候変動による悪影響をいかに回避するかという点に主眼が置かれているが、一方で、気候変動を受け入れ、悪影響を軽減したり、逆手に取ってポジティブに捉えたりする点に市場機会を見出す方向性も存在する。都市・インフラや服装・身の回り品の完全防水や、豪雨や落雷による音の恐怖の軽減、日照が減るストレスに対応し太陽を模した照明など、新たな製品・ソリューション開発の可能性がある。(「ポスト温暖化の未来予測」[ⅲ])また、開発当初から意識されていなかったとしても、上記のような製品・ソリューションは結果として気候変動への“適応”に貢献しうるケースもあり、リブランディングすることも可能であろう。

5.結論
今回、気候変動への“適応”の重要性と、企業が戦略・打ち手として“適応”に取り組む意義について論じてきた。企業のサステナビリティ戦略の視点において、気候変動への物理的リスクは、市場機会として捉えられることで戦略・打ち手に反映される可能性が十分にある。さらに、気候変動により気象情報の価値が向上することで、気象ビジネスへの期待も膨らむものと推察される。したがって、今後は民間企業が個社としても、業界全体としても、気候変動への“適応”について、産業・ビジネスの視点でリスクの観点のみならず、機会も含めて検討することが重要である。
ただし、産業やビジネスの視点で気候変動への“適応”を考えることは、“緩和”をおろそかにしていいということではない。“適応”のために重要となる気候変動による影響の予測・洞察についても、非線形理論で知られているように、変動の幅が大きくなればなるほど予測が困難になるため、平均気温上昇幅が小さいに越したことはない。したがって、気候変動への“適応”を検討するためにも、脱炭素による“緩和”を進めていくことが絶対条件になる。つまり、“緩和”と“適応”は相互補完的なものと理解し、両方推進していくことが重要といえる。
【関連レポート・コラム】
ポスト温暖化の未来予測~温暖化が抑制できないケースの心積もりの重要性~
【関連サービス】
サステナビリティ(環境・資源・エネルギー・ESG・人権)
参考文献
[ⅰ] 帝国データバンク「温室効果ガス排出抑制に対する企業の意識調査」(2021年1月)
[ⅱ] 気候変動適応情報プラットフォームHP
[ⅲ] 当社レポート「ポスト温暖化の未来予測~温暖化が抑制できないケースの心積もりの重要性~」(2021年8月20日)
[ⅳ] TCFDコンソーシアムHP
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。