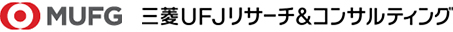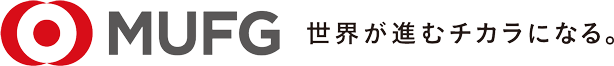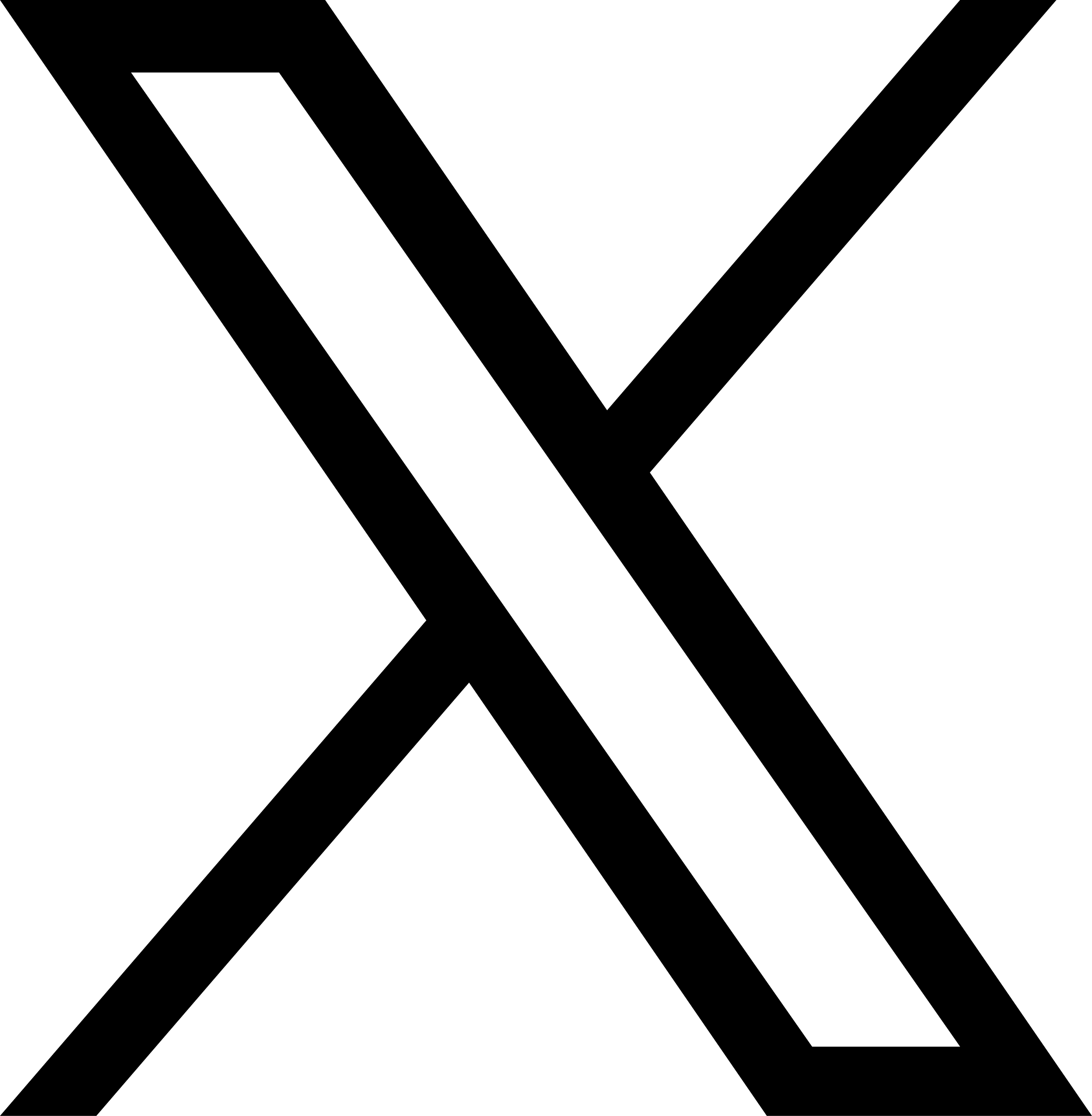転換点を迎えたビジネスデザイン~シリーズ「食品産業のプラスチック包材にみるサステナビリティ」①~
連載「食品産業のプラスチック包材にみるサステナビリティ」では、食品産業界における食品パッケージのプラスチック包材廃棄物を手掛かりに、今後の日本企業に求められる対応のあり方や取り組みの可能性などを深掘していく。本稿では、グローバル企業におけるプラスチック包材や製品パッケージのデザインの見直しやビジネスデザインの概況について説明する。
1. 強化が求められるプラスチック包材への対策
19世紀に発明されたプラスチックは、安価で成形しやすい特性から、木材や金属に代わる実用的な素材として日常生活に普及し、現代社会において欠かせない存在となった。しかし近年、プラスチックにおける負の側面を照らす光が強さを増している。
ペットボトルのように、世界的にリサイクルの仕組みが確立されているプラスチック製品がある一方、全体の約4割は、使い捨てプラスチック(特に包材として使用)といわれている。ごみ袋や食器、ストローなどに代表される使い捨てプラスチック製品は、回収率・リサイクル価値が低い。そのうえ、食品との接触による安全衛生上の理由により、特に途上国ではその多くが回収されないまま自然環境の中へと流出したり、リサイクルされずに野積みされたままになっている。また、強度やバリア性などを高めるために、プラスチックとアルミ箔といった異なる素材を張り合わせて高機能化されたパウチなどの軟包材は、技術的にもリサイクルが困難である。
世界的な使い捨てプラスチック廃止の流れの中で、企業に対してプラスチック包材への対策が一層強く求められ始めている。2018年1月、欧州連合(EU)は「循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略」(通称「EUプラスチック戦略」)を策定し、2030年までにすべてのプラスチック容器を再使用、またはリサイクルすることを表明した。EUは2018年5月にはストローをはじめとする使い捨てプラスチックの規制案を発表し、2019年5月に採択された。この中では、各種使い捨てプラスチックに対する使用禁止の他、企業に対して拡大生産者責任の考え方が適用され、使用済み製品の廃棄物処理の責任が企業に求められることとなった。再使用やリサイクルが困難な軟包材までには及んでいないが、使い捨てプラスチックの有料化などの規制は、すでにトルコ、ペルー、ベトナム、カンボジア、マレーシアなどにおいて国レベルでの導入が進んでいる。以下では、グローバルメーカーによるプラスチック包材廃棄物への取り組み事例を通じて、日本企業に求められる対応を考えてみたい。
2. プラスチック包材と製品パッケージの見直し
世界的にプラチック包材廃棄物への目が厳しくなる中で、企業は包材および製品パッケージの再設計を進めている。これには「減らす」と「置き換える」の2つの方向性がある。プラスチック消費量を減らす取り組みとしては、使い捨て容器を詰め替え用の包材に置き換えたり、包材自体を薄型化や小型化する、あるいはストローなどのプラスチック製付属物は廃止するなどが代表的な例である。たとえばネスレ(Nestlé)は、東南アジアで販売されている「ネスカフェ」(Nescafé)を始めとした商品パッケージの小型化や薄型化を進め、こうした取り組みを通じてプラスチック包材使用量を2015年から2019年の期間で14.2万トン削減した。
プラスチック包材を「置き換える」方法にもいくつかパターンがある。その1つは、素材を環境に優しいものへと切り替えることである。リサイクルしやすいように原料を単一素材としたり、生物由来や、自然界で早く分解される素材の使用などが行われている。たとえばユニリーバ(Unilever)はトルコでクノール(Knorr)粉末スープの包装を単一原料由来の素材へと切り替えている。また、リサイクルがより容易なプラスチック以外の包材へ切り替える方法もある。ネスレは、フランスで販売されているマギー(Maggi)コンソメキューブの包装をアルミ箔から紙ベースの包材に切り替えた。
包材の見直しがビジネス上の大きな成功をもたらすケースもある。パキスタンでは、国内大手乳業メーカーのエングロ・フーズ(Engro Foods、現FrieslandCampina Engro Pakistan)が、2013年に250ミリリットル入りのロングライフ牛乳「オルパーズ」(Olper’s)の容器を、現地でのリサイクルが不可能な軟包材(アルミコーティングを施した紙パック)から、スウェーデンのエコリーン(Ecolean)社が開発したリサイクル可能なプラスチック包材(減容(容積を減少)化されて一般的な方法でリサイクル可能)へと切り替えた。ユニークでモダンな形状の新パッケージが顧客への大きなアピールポイントとなり、包材置換後の僅か18カ月で売上は倍増した。また、2005年に誕生した同新興ブランド(オルパーズ)が、ネスレの「ミルクパク」(MilkPak)から市場占有率首位獲得の一翼を担った。
3. ビジネスデザインの見直し
多くの企業においてプラスチック包材の見直しが進む中、企業の取り組みに対して、包材を見直す以上の責任を求める潮流は強まっている。循環経済への移行を促進する世界的にも有力な団体であるエレン・マッカーサー財団(Ellen MacArthur Foundation)は、「ニュー・プラスチック・エコノミー・グローバル・コミットメント」(New Plastic Economy Global Commitment)に参加する企業に対して、2025年までのプラスチック廃棄物削減目標とそれに向けた行動計画を自主申告するように求めている。これに賛同するネスレ、ユニリーバ、ペプシコ(PepsiCo)をはじめとするグローバルメーカーは、製品それ自体でなく、開発から調達・生産・販売後に至る一連のビジネスデザインを世界規模で見直し始めている。以下では、こうした取り組みの中から3つの類型を事例とともに取り上げたい。
【図表1】エレン・マッカーサー財団の活動方針と署名団体

(出所)資料を基に当社作成
(1)調達プロセスの再設計
1つ目は、調達プロセスを倫理的かつ持続可能なものにしようとする取り組みである。ネスレは責任ある調達に関するガイドラインを設け、主要な原料については当ガイドラインに従ってサプライヤーから調達している。ペルーにおいて、同社はパーム油最大のバイヤーであるが、同社による調達が無秩序な農地転用による森林破壊をもたらさないように、国内外のステークホルダーと協業を推進している。
(2)流通プロセスの再設計
2つ目は、流通方法の再設計により、配送段階での梱包資材や店頭販売用のパッケージングを削減する試みである。米国のリサイクル事業者テラサイクル(Terra Cycle)の「ループ」(Loop)イニシアチブには、ネスレ、ユニリーバ、ペプシコ、モンデリーズ・インターナショナル(Mondelez International)などの食品メーカーが参加している。ループはEコマースのビジネスモデルであるが、参加企業各社の商品は、年単位での再充填(数年間、何度も届けて、回収して、詰めなおして、また売って、といった活動に耐える容器のこと)が可能な容器に入って販売されている。ループを通じて購入された商品は、再利用可能な専用トートバッグに入れられて配送されるほか、使用後の容器は、回収・洗浄され、再充填後に改めて出荷されることとなる。
(3)回収・リサイクルプロセスの再設計
3つ目は、回収・リサイクルに新たな仕組みをもたらす取り組みである。ネスレやダノン(Danone)などが立ち上げた団体「3Rイニシアチブ(3R Initiative)」は、ミャンマーでプラスチック廃棄物における世界で初めて仮想取引市場の創設を目指して取り組んでいる。この市場では、収集・処理されたプラスチック廃棄物を回収量に応じて「クレジット」という仮想取引通貨で排出企業が買い上げる。これにより企業は、これまで直接取引相手とはなりにくかった個人との取引が可能となるため、回収・リサイクル量を予算に合わせて市場でフレキシブルに調整できる。また、個人との取引におけるクレジット購入は、回収・リサイクル事業の支援や自社廃棄物排出量を購入した回収・リサイクル量で、相殺することも可能となる。
【図表2】3Rイニシアチブの市場メカニズムを利用したプラスチック回収モデル

(出所)3R Initiativeホームページ:
“Circular Action Hub: Scaling-up Collection & Recycling by Driving Finance to Local Projects” (2021年9月21日確認)
4. 日系メーカーに求められるプラスチック包材廃棄物へのアプローチ
【図表3】日系メーカーと世界的なトレンドによるプラスチック包材廃棄物へのアプローチ

(出所)資料を基に当社作成
近年、世界的にプラスチック廃棄物に対する風当たりが強まる中、図表3でみるように、世界的なトレンドとなっているグローバルメーカーは、製品を売るだけで終わりにしていない。流通を含む製品ライフサイクルの終了から再循環までを視野に入れ、ビジネスモデル全体の転換に取り組んでいる。一方、多くの日系メーカーはこうしたビジネスモデルの再設計が必要となるようなサステナビリティに関する重要業績評価指標(KPI)を設定しておらず、結果として直接推進するのは包材の見直しに留まっている。また、ビジネスモデルの再構築に取り組んでいる場合でも、現状は日本国内での取り組みに留まることが一般的である。しかし、世界的な潮流に鑑みれば、グローバルメーカーが推進するこれらの取り組みは、日系メーカーにも近い将来求められることに他ならないだろう。
参考文献
・Ecoleanホームページ:Ecolean“Olper’s ”(2021年9月21日確認)
・エレン・マッカーサー財団ホームページ:“New Plastic Economy Partners ”(2021年9月21日確認)
・経済産業省ホームページ:経済産業省“プラスチックを取り巻く国内外の状況<参考資料> ”(2021年9月21日確認)
・Swissinfoホームページ:Dupraz-Dobias, Paula“Can Nestlé source Peruvian palm oil without deforestation? ”(2021年9月21日確認)
・Nestléホームページ:Nestlé“What is Nestlé doing to tackle plastic packaging waste? ”(2021年9月21日確認)
・National Geographicホームページ:Parker, Laura“The World’s plastic pollution problem explained ”(2021年9月21日確認)
【専門用語集】
| 掲載回 | 専門用語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | サステナビリティ(Sustainability) | 環境・社会・経済の観点から、持続可能にしていくという考え方のこと。 |
| 1 | リサイクル | 廃棄物や不用物を回収・再生し、再資源化、再利用すること。 |
| 1 | パウチ | 強度やバリア性などを高めるために、プラスチックやアルミ箔など異なる素材を張り合わせて高機能化された軟包材のこと。 |
| 1 | 循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略 | 2018年1月、欧州連合は「循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略」(通称「EUプラスチック戦略」)が策定された。 |
| 1 | 減容 | 容積を減少させる。 |
| 1 | 責任ある調達 | サプライチェーンの各段階において、倫理的かつ持続可能な製品やサービスの積極的な調達を、企業が確実にしていることを意味する。 |
| 1 | 3Rイニシアチブ(3R Initiative) | 従来の3Rとは廃棄物の削減(Reduce)、資源や製品の再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)を指す。ただし、ここでの3Rイニシアチブの3Rは、前出の3Rとは少し異なり、資源や製品の再使用(Reuse)⇒資源や製品の回収(Recover)となり、ネスレやダノン(Danone)などが立ち上げた団体を指す。 |
| 1 | 重要業績評価指標(KPI) | 目標達成に不可欠とされる業績管理評価のための指標のこと。 |
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。