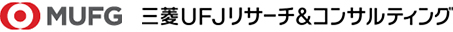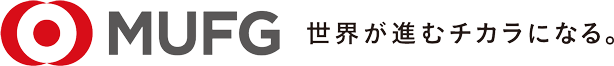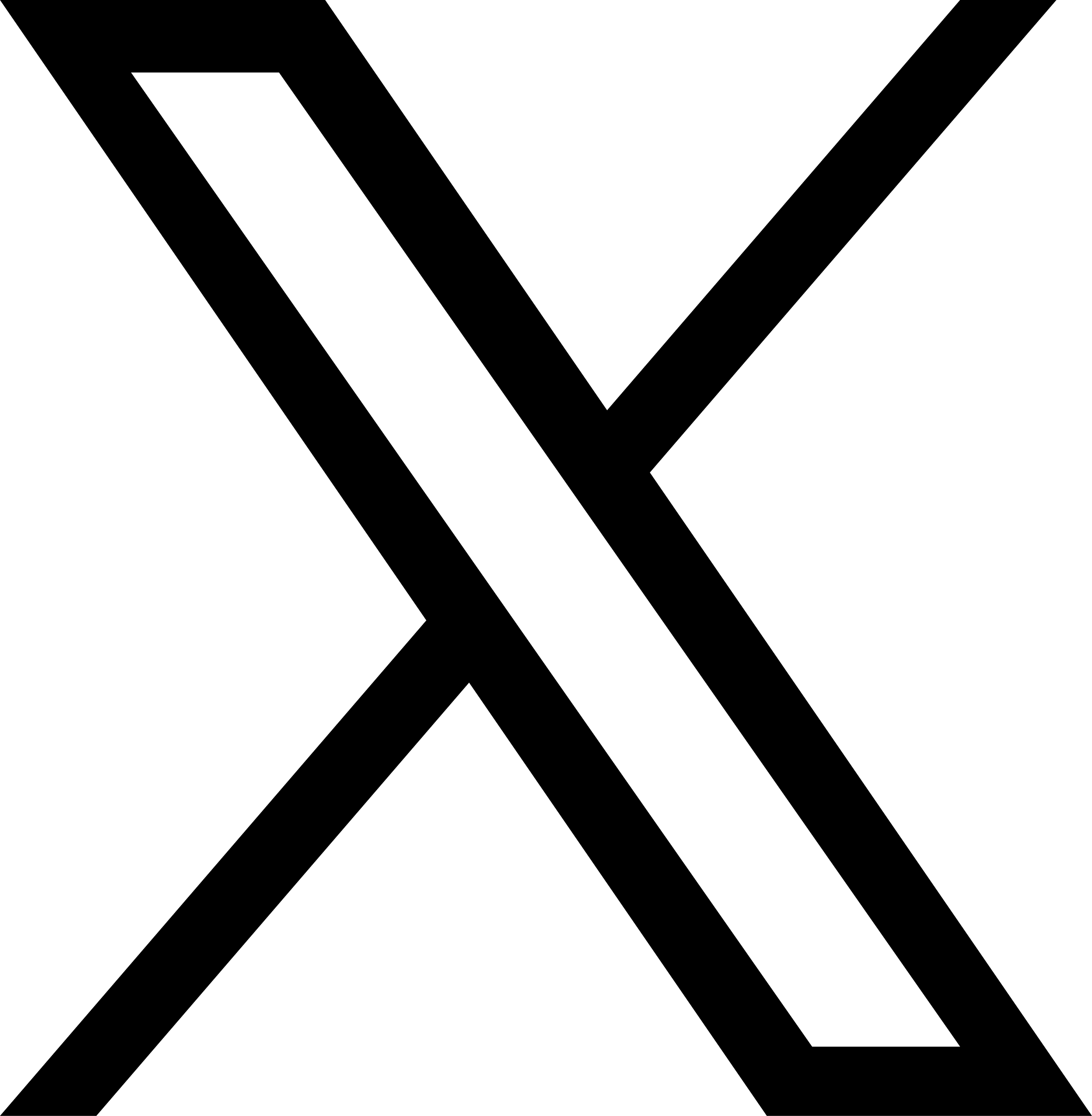- コロナ禍の拡大後(2020年1月より後)に、在宅勤務を初めて行った労働者の身体面での健康意識の変化をみると「体力の低下」(34.7%)が高い割合を占めている。本稿では、在宅勤務に伴う体力の低下の背景を明らかにするとともに、関連する労働者の健康意識等との関連や業務効率への影響をみた。
- 体力の低下の背景として各種の時間変化との関係をみると、「通勤・業務で歩いたりする時間」、「通勤・業務以外で体を動かす時間」といった身体を動かす時間の減少に加えて、「仕事仲間・顧客等とのつきあいの時間」といった対人的な関係性や活動の維持・強化の機会減少と関連がみられた。一方で仕事の時間、業務で座っている時間変化と体力変化との明確な関連はみられない。
- 在宅勤務による体力の変化と健康のための(本人の)取組(実施)状況の関係をみたところ、在宅勤務により、何らかの理由で適度な運動が『難しい』場合、「体力が低下した」と意識している割合が高いことが分かった。通勤・業務や通勤・業務以外で身体を動かす機会の減少、仕事仲間・顧客等とのつきあいでの対人的な関係性や活動の維持・強化の機会の減少に対して、適度な運動の実施により補うことが難しいと、体力の低下意識を顕著に感じていることがうかがわれる。
- 体力の低下と運動機能や主観的な健康状態、業務の効率・発揮度がどう関連しているかを確認した。結果をみると、「いすに座った状態から、片足だけで立ち上がれるか」という運動機能の一つの指標ではあるものの、体力の低下との関連がうかがわれる状況であった。また、「体力が低くなった」人では主観的健康観が低い人の割合が相対的に高く、体力の低下がその後の健康とも関連する可能性があることが示唆された。さらに健康状態が万全の時を100とした場合の「業務の効率・発揮度が高い/低い」割合は、「体力が高くなった/低くなった」人でそれぞれ高くなっていた。こうした結果からは、在宅勤務者の体力の低下が、身体面、精神面両方と関連していることがうかがわれる。なお、メンタルヘルスの状態として、K6尺度(うつ病・不安障害等の精神疾患のリスク)については、体力の変化による違いはみられなかった。
- 勤め先が労働者の健康管理・増進に対してコロナ禍以前(2020年1月以前)から取り組んでいる場合には、在宅勤務者が実際に運動をしている割合が高いことから、勤め先が労働者の健康管理・増進に継続的に取り組むことで、労働者の運動が促進されると考えられる。また、勤め先が、『運動』に関する直接的な取組に限定せず、食事・栄養、ストレス解消・メンタルヘルス等に関する情報提供や研修・イベントの実施、あるいは相談対応などを幅広く推進することで、在宅勤務者自らの運動行動につながっていることが示唆された。
- 勤め先が労働者の健康管理・増進に継続的に取り組むことは、在宅勤務者の運動行動につながっており、在宅勤務者の業務の効率・発揮度が高い傾向がみられた。こうした取組は、労働者本人のみに留まらず、企業にとっても意義・効果があることが示された。
【シリーズ「在宅勤務は何をもたらすか」タイトル一覧】
① 在宅勤務者の人数規模と属性
② 在宅勤務に伴う家事・育児時間及び運動時間の変化
③ 在宅勤務者のメンタルヘルスの現況
④ 在宅勤務に伴う「体力」の低下・・・<本稿>
⑤ 在宅勤務者の仕事のモチベーション・効率性に影響を及ぼす要因の検討
⑥ 在宅勤務を成功させるために必要な企業の取組
テーマ・タグから見つける
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。
テーマ
テーマ