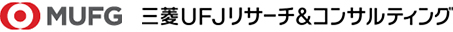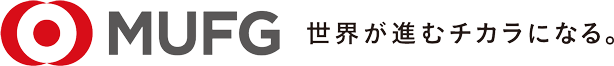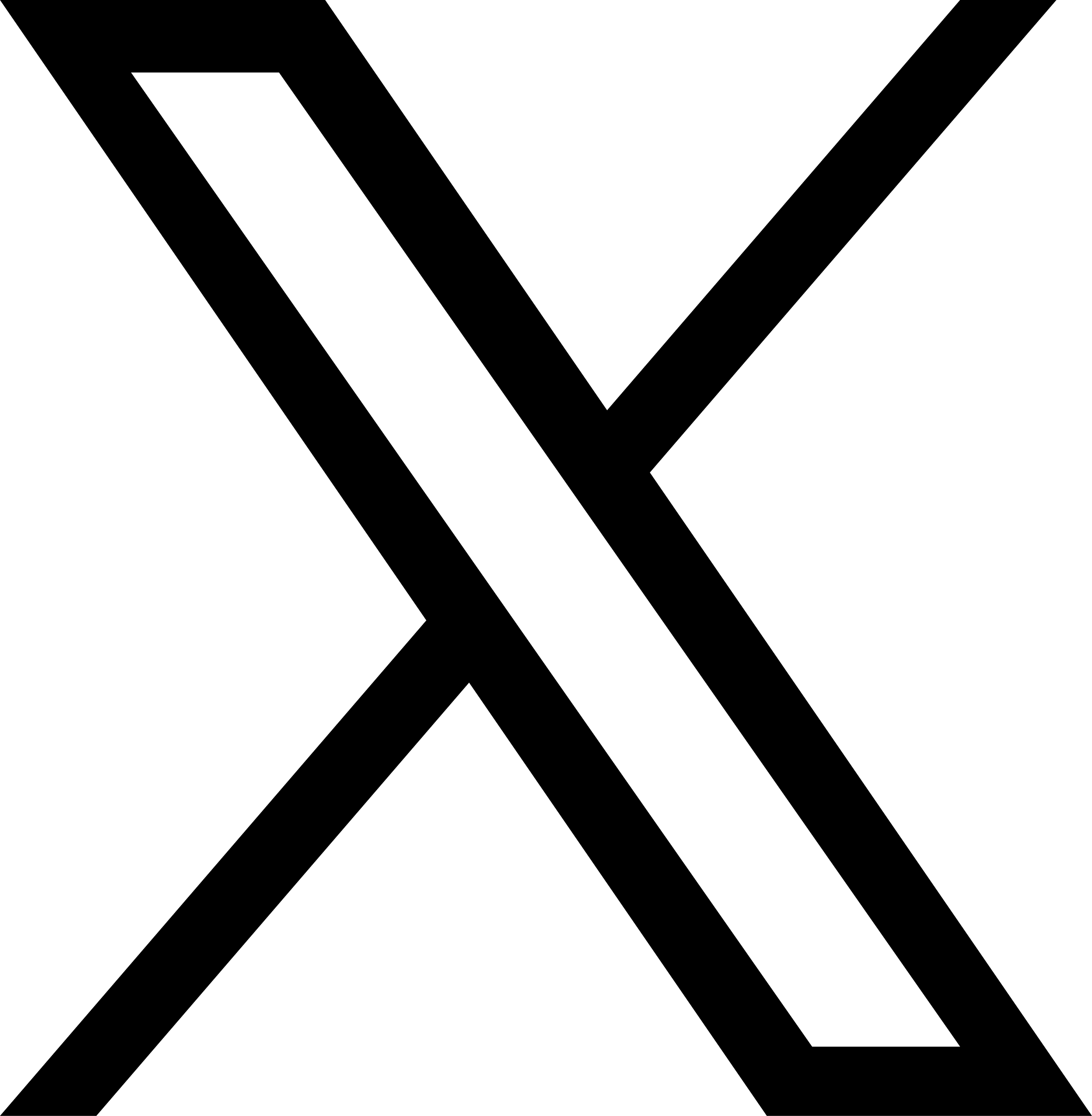外国人高齢者の「助けて」に寄り添う~「外国人高齢者に関する調査」報告書~
日本国内に居住する外国籍の高齢者は2022年末で約20万人(10年前の1.5倍)となり、日本の高齢者の約180人に1人は外国籍である。しかし、多くの地域では外国人高齢者が行政等の関係機関とつながる機会が少なく、困りごとを抱えていても支援が届きにくい状況にある。本調査では、東京都渋谷区等を拠点に活動する関係機関・団体等へのヒアリング調査・アンケート調査を実施し、外国人高齢者の抱えている困難について実態を把握するとともに、今後必要な支援の施策について検討を行った。
なお、東京都渋谷区内の関係機関については、渋谷区のご協力を賜ることでヒアリング調査・アンケート調査の実施が実現した。渋谷区に対し、この場を借りて厚くお礼申し上げたい。
【要旨】
外国人高齢者の現状と支援体制の課題
● 外国人高齢者の中には、困りごとがあっても支援を希求できず本人・家族で抱え込み、状態が深刻化してしまう人も少なくない。
● 本調査では、外国人高齢者の現状として、以下の点が把握された。
外国人高齢者の「助けて」の見えづらさ
- 社会的孤立
- 関係機関へのつながりにくさ
- 関係機関につながった時点では問題が深刻化している傾向
外国人高齢者が抱えている困難
- 言語に関する問題
- 介護保険サービスに関する理解不足
- 外国人高齢者が利用しやすいサービスの選択肢の少なさ
- 病気や障害に関する誤解
- 老後の蓄えが不十分
支援者(ケアマネジャー、介護施設・事業所等)が感じている支援の難しさ
- コミュニケーションに関する課題
- 外国人高齢者の支援に活用できるサービス等や情報の不足に関する課題
- 関係機関との連携に関する課題
国・自治体に求められる施策
● 国・自治体においては、今後、次のような施策が求められる。
- 外国人高齢者にとっての身近な相談先の確保・連携
例)同国人コミュニティや母語で気兼ねなく交流できる場(居場所)/日本人を中心とするコミュニティで外国人高齢者が気軽に参加しやすいもの - 支援が必要な人を取りこぼさない相談支援体制
例)どこの行政窓口相談があった場合でも相談を受け止め、必要な対応(他部署・機関への連絡も含む)につなげる/外国人向け相談窓口の設置 - 介護保険制度の周知(若い世代の外国人も含む)
例)65歳を迎えたタイミングで、多言語で作成された介護保険制度に関するチラシ等を配布/介護保険料の納付を開始するタイミングでの説明 - 既存の資源の活用と新たな資源の開発
例)外国人高齢者へのケアの充実という観点からも、外国人介護人材の育成および活躍を支援/行政区を広くまたいで活動する支援団体、対象者の属性を問わず対象としている生活支援サービス等との連携・協働 - 支援者が支援しやすくなるための仕組みづくり
例)いつでも専門的な通訳サービスが利用できる体制づくり/支援者のスキルアップ支援、支援者同士で相談・情報共有ができる場の提供
● 日本は今後一層、多くの外国人労働者とその家族を受け入れていくことになるが、その人々が日本で年齢を重ね、いずれ高齢期や終末期を迎えていくことを前提に、受け入れ環境の整備を行っていく必要がある。
● 本調査では、外国人高齢者の支援ニーズが顕在化していない地域も含めて、実際には多くの支援における課題があることが分かった。各自治体においては、地域の外国人高齢者の実態把握や、それを踏まえた支援の仕組みづくりを行っていくことが求められる。
※(2024年6月3日訂正)レポート中に以下の通り誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
・9ページ (1)インタビュー調査の概要
首都圏中国帰国者支援・交流センターの所在地
正:東京都台東区
誤:東京都渋谷区
・25ページ 【図表20】
注釈を追記
・17ページ、25ページ、29ページ
単位表記の修正
訂正箇所詳細は正誤表をご確認ください。
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。